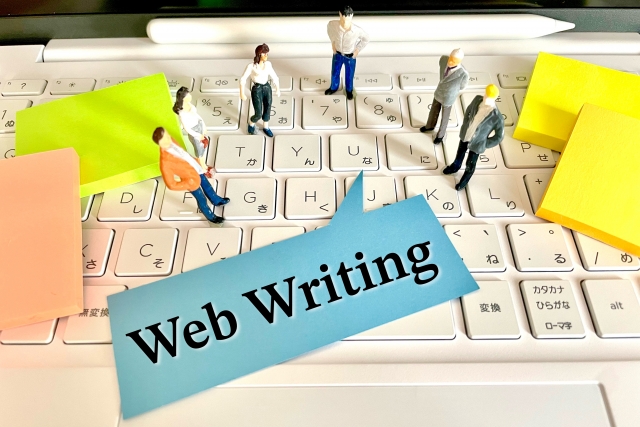はじめに
この記事は、Web制作とWeb開発の違いを、やさしく丁寧に解説します。名前は似ていますが、役割や求められるスキル、担当範囲は異なります。例えば、企業の採用サイトを作る場面では、見た目や文章、写真を整えるのが「制作」、応募フォームやデータ保存などの仕組みを作るのが「開発」です。
目的は二つあります。ひとつは、発注時に適切な担当を選べるようにすること。もうひとつは、これからのキャリア選択でどちらが自分に合うか判断できるようにすることです。
対象は、発注担当者、個人事業主、これから学ぶ人など広く想定します。専門用語は最小限にし、具体例を交えて説明します。読み進めると、各章で業務範囲、必要なスキル、ワークフロー、職種の違いと、最終的にどちらを選ぶかの判断基準が分かります。
まずは全体像を把握して、必要な部分を深掘りしていきましょう。
Web制作とWeb開発の定義・目的の違い
全体の違い
Web制作は見た目や使いやすさを作る仕事です。色やレイアウト、文章の見せ方に注意し、訪問者に伝わりやすいページを作ります。Web開発は機能を作る仕事です。データのやり取りや処理、ユーザーの操作に応じた動作をプログラムで実現します。
Web制作(フロントエンド)の目的と具体例
目的はユーザーにとって分かりやすく魅力ある画面を提供することです。具体例は次の通りです。
– 企業のコーポレートサイトやランディングページのデザイン
– スマホでも見やすいレイアウト作成(レスポンシブ対応)
– ボタンやメニューなどの操作性向上
制作の段階では、ワイヤーフレームやデザインカンプを作り、HTML/CSSで見た目を組み立てます。
Web開発(バックエンド・システム系)の目的と具体例
目的はサイトに動きやデータ処理を持たせることです。具体例は次の通りです。
– お問い合わせフォームの送信先処理やメール通知
– 会員登録やログイン機能、権限管理
– ショッピングカートや決済連携、注文管理
– データベースや外部APIとの連携
開発ではサーバーやデータベースの設計、プログラムでの処理実装が中心になります。
日常的な区別ポイント
見た目を整える作業が中心なら制作寄り、処理や仕組み作りが多ければ開発寄りです。小規模な案件では一人で両方を担当することもあります。役割が重なる点は多いので、依頼時は「見た目だけか」「機能も必要か」を明確に伝えるとスムーズです。
業務範囲と担当領域の違い
概要
Web制作は画面の見た目や使いやすさを作ります。Web開発は裏側の仕組みや機能を作り、サイトを動かします。
Web制作(担当:Webデザイナー、フロントエンド)
- 視覚デザイン:色・タイポ、レイアウトを決める
- UI/UX設計:導線やワイヤーフレーム、プロトタイプ作成
- コーディング:HTML/CSSやJavaScriptで見える部分を実装
- レスポンシブ対応、アクセシビリティ、画像や素材の準備
- デザインシステムやスタイルガイドの整備
具体例:商品ページのレイアウト、ボタンの見た目やアニメーションの設計
Web開発(担当:Webエンジニア、バックエンド)
- サーバーやインフラの構築と運用
- データベース設計とデータ管理
- APIや業務ロジックの実装(認証、決済、検索など)
- セキュリティ対策、性能改善、監視・ログ管理
- デプロイやCI/CDの設定、テスト自動化
具体例:注文処理の流れ、ログイン認証、データ保存の仕組み
境界と重なる領域
- API仕様やデータ形式の合意が必要
- コンポーネント受け渡しや動作確認で工数が重なる
- アクセシビリティやパフォーマンス改善は共同作業になる
連携のポイント
- 早い段階でAPI仕様やデータ構造を決める
- モックデータやスタブで並行作業する
- デザインガイドやコンポーネントを共有する
- ステージング環境で統合テストを行い、ドキュメントを残す
担当範囲を明確にし、こまめにコミュニケーションすることで開発がスムーズになります。
必要なスキル・使用言語の違い
概要
Web制作は見た目と使いやすさを作る仕事で、HTML・CSS・JavaScriptを中心に使います。Web開発は仕組みや処理を作る仕事で、Java・Python・PHP・Ruby・SQLなどを使います。
Web制作で求められるスキル
- マークアップ言語(HTML)で構造を作ります。例:見出しや段落を正しく配置します。
- 見た目を整える(CSS)。例:配色、余白、レスポンシブ対応。
- 動きをつける(JavaScript)。例:メニューの開閉や画像スライド。
- デザインツール操作(Figmaなど)や画像最適化、アクセシビリティの知識も必要です。
Web開発で求められるスキル
- サーバー側の言語(例:Java、Python、PHP、Ruby、Node.js)で処理を作ります。
- データを扱う(SQLやNoSQL)。例:ユーザー情報の保存や検索。
- API設計、認証、セキュリティ対策、テスト、デプロイの知識が求められます。
- Gitなどのバージョン管理やコマンドライン操作もよく使います。
重視される力の違い
制作は表現力とユーザー視点を重視します。開発は安定性や拡張性、効率よく処理する力を重視します。
学び方のポイント
最初は制作の基礎(HTML/CSS)から始めると全体が見えます。バックエンドに進む場合は一つの言語とデータベースを深めると習得が早まります。
ワークフロー・プロセスの違い
概要
Web制作とWeb開発は目的と工程が重なる部分もありますが、進め方や関係者が異なります。本章では代表的な作業の流れと実務での違いを分かりやすく説明します。
Web制作の一般的なワークフロー
- 要件確認(目的・ターゲット・ページ構成)
- ワイヤーフレーム作成(レイアウトと導線を決める)
- デザイン作成(ビジュアルの完成)
- コーディング(HTML/CSS/JSで見た目を実装)
- テスト・公開(表示確認・軽微な調整)
制作は見た目とユーザビリティに重点を置き、短いサイクルで進みます。成果物はデザインカンプや静的なHTMLが中心です。
Web開発の一般的なワークフロー
- 要件定義(機能、データ、非機能要件の整理)
- システム設計(アーキテクチャ、データベース設計)
- 実装(サーバーサイド、API、フロント実装)
- テスト(単体・結合・負荷など幅広く実施)
- デプロイ・運用(CI/CD、監視、障害対応)
開発は技術的な整合性や運用性を重視し、長期の保守も見据えます。
主な違いと連携ポイント
- 粒度:制作はページ単位で進み、開発は機能単位で設計します。
- 関係者:制作はデザイナー主体、開発はエンジニアやインフラ担当も加わります。
- テスト範囲:制作は表示確認中心、開発は機能・性能・セキュリティまで行います。
発注時はそれぞれの工程と成果物を明確にし、早期に要件を共有するとスムーズに進みます。
職種と役割の違い
概要
Web制作とWeb開発では、関わる職種が異なり、それぞれ役割の範囲や求められるスキルが変わります。ここでは代表的な職種を挙げて、日常の業務と関係性を分かりやすく説明します。
Web制作の主な職種
- Webデザイナー
- 役割:見た目やレイアウト、色使いを考えます。用途に応じたデザイン案を作り、紙や画像で提案します。
- 例:トップページのビジュアルやバナーを作る。
- コーダー
- 役割:デザインをブラウザで表示できる形に組みます(HTML/CSS)。動きの簡単な調整も担当します。
- 例:レスポンシブ対応や画像最適化を行う。
- フロントエンドエンジニア
- 役割:ブラウザ側の動きをプログラムで実装します。ユーザー操作に応じた動作を作ります。
- 例:スライダーやフォームの入力チェックを作る。
- Webディレクター
- 役割:進行管理や要件整理、クライアントとの折衝を行います。制作チームの指揮をとります。
- 例:要件をまとめ、スケジュールを作る。
Web開発の主な職種
- Webエンジニア
- 役割:全体の仕組みを設計・実装します。サーバーとデータのやり取りを扱います。
- 例:会員登録機能の設計と実装。
- バックエンドエンジニア
- 役割:サーバー側で動くロジックやデータベース処理を担当します。性能や安全性に配慮します。
- 例:検索機能の高速化やAPIの作成。
- システムエンジニア(SE)
- 役割:要件定義から設計、運用方針まで幅広く関わります。プロジェクト全体の技術的判断をします。
- 例:システム構成や運用手順を決める。
- フルスタックエンジニア
- 役割:フロントもバックも担当できる人材です。小〜中規模の開発で活躍します。
- 例:要件に合わせて画面とAPIの両方を実装する。
連携のポイント
制作側は見た目と使い勝手を、開発側は仕組みと性能を重視します。早い段階で役割をすり合わせると、実装や納品がスムーズになります。
どちらを選ぶべきか・発注のポイント
選ぶ基準
見た目やブランドを重視し、情報を中心に伝えたい場合はWeb制作に向きます。たとえば会社案内や採用ページのように更新頻度が低い静的サイトです。一方、会員登録、予約、決済、業務データのやり取りなど複雑な処理が必要ならWeb開発を選んでください。ECサイトや業務システムが該当します。
発注前に決めること
必須機能とあると便利な機能を分け、予算と納期を明確にします。既存のサービス(会計や予約)の連携があるか、CMSを使いたいか、運用を社内で行うか外注するかを決めておくと見積もりが正確になります。
発注時のチェックリスト
- 目的と想定ユーザー
- 必要な機能(優先順位つき)
- 参考サイトやデザイン要望
- 予算と納期
- テストと受け入れ基準
- 保守・運用範囲
契約と保守のポイント
納品物(デザイン、静的ファイル、ソース、説明書)を明記し、バグ対応やセキュリティ更新の期間と費用を契約に入れます。運用後の改修や追加は都度見積もりにするか、保守契約でカバーするかを決めてください。
まとめ・両者の連携
要点のまとめ
Web制作(見た目・使いやすさ)とWeb開発(機能・安定性)は役割が異なります。どちらもユーザー体験に直結しますので、片方だけが優れていても満足度は下がります。両者が揃って初めて価値あるサイトができます。
連携のポイント
- 早い段階で共通の目的を決める(ターゲット、KPI、必須機能)
- デザイン段階で開発の制約を共有する(例: ページ数や動作の重さ)
- 開発段階でデザインの意図を守る(色や余白、操作の流れ)
実務での具体例
- デザイナーがプロトタイプを作り、開発者が動作確認を行う
- 開発者が負荷のかかる機能を提案し、デザイナーがUIを簡素化する
- 共通のチェックリストでアクセシビリティや表示崩れを防ぐ
発注者へのアドバイス
- 最初から制作と開発の担当を明確にする
- 小さな段階でレビューを重ねる
- 見た目と機能、両方の観点で評価基準を用意する
丁寧な連携があれば、見た目も機能も両立した使いやすいWebサイトを作れます。