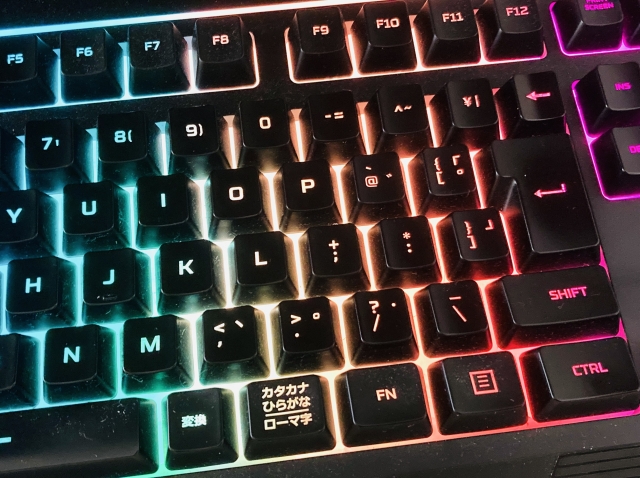はじめに
本ドキュメントの目的
本書は、Webサイト制作の流れを企画から公開までわかりやすく整理したガイドです。制作全体の見取り図を示し、各工程で何を確認すべきか、どのように進めればスムーズかを伝えます。制作会社と話す際のポイントも具体例で解説します。
想定する読者
・これから自社サイトやサービスサイトを作る担当者
・制作の発注や進行管理に不安がある方
・フリーランスや小規模チームでサイトを作る方
専門用語をなるべく避け、初めてでも理解しやすい説明を心がけます。
この記事で学べること
・制作の主要なステップ(企画、設計、デザイン、実装、公開、運用)の全体像
・各工程での確認事項や失敗しやすい点と対策
・制作期間の目安と効率化のコツ
具体的な例をあげながら、実務で使える知識を提供します。
読み方のポイント
章ごとに順を追って読めば全体像が掴めます。すでに進行中の方は、該当する章だけ先に読むのも有効です。実際の発注や打ち合わせ資料作成に役立つチェックリストも用意します。
Web制作の全体像
Webサイト制作は目的を明確にして段階を追って進めます。ここでは代表的な工程をわかりやすく説明します。
企画
- 目的設定:何のために作るか決めます。例:問い合わせを増やす、商品を紹介する。
- ターゲット分析:誰に届けたいか具体的に想像します(年齢・興味など)。
- 競合調査:似たサイトを見て良い点・悪い点を洗い出します。
設計
- サイトマップ作成:ページ構成を設計します。
- ワイヤーフレーム:各ページの骨組みを作ります。例:トップにバナー、下部に問合せフォーム。
- システム設計:必要な機能(CMS、会員機能など)を決めます。
デザイン
- デザインカンプ制作:見た目の最終案を作ります。
- 素材準備:写真やイラスト、ロゴを用意します。
実装
- HTML/CSSコーディング:表示を作ります。
- CMS構築/開発:更新しやすくします。
- テスト:動作や表示を確認します。
コンテンツ制作
- 文章・画像・動画:伝わる表現を作ります。例:商品説明に写真と短い動画を付ける。
テストと公開
- 動作確認・ブラウザチェック:実際の見え方と動きを確認します。
- 公開作業:サーバーにアップし、DNS設定を行い一般公開します。
各工程は重なり合いながら進みます。小さな改善を繰り返すことで、より良いサイトになります。
各工程の詳細とポイント
企画フェーズ
目的とゴールを明確にします。例えば「月間問合せ数を30件に増やす」「商品の認知を高める」など、数値目標を置くと判断が楽になります。ターゲットは年齢・職業・利用シーンで具体化します(例:30代共働き、スマホ利用中心)。競合分析は機能・価格・表現を比較し、差別化ポイントを決めます。RFPは要件、予算、納期、検収条件を盛り込みます。
設計フェーズ
サイトマップで構成と導線を固めます。重要ページを洗い出し、CTA(行動促進)を明確にします。ワイヤーフレームは画面ごとの要素配置を作り、優先度を示します。システム設計では必要な機能(会員、決済、フォーム等)とデータの流れを図にします。
デザインフェーズ
ビジュアルはブランドと目的に合わせて決めます。色やフォントは読みやすさと印象を優先します。素材は高画質画像、短めの動画、アイコンを準備し、必要なら撮影や素材購入を行います。
実装・コーディング
フロントはHTML/CSS/JavaScriptで視認性と動作を作ります。アクセシビリティと表示速度を意識します。バックエンドはCMSやAPIで運用性を高め、セキュリティ対策も講じます。レスポンシブ対応は主要な画面幅で崩れないかを確認します。
コンテンツ制作
テキストは読み手の疑問を先回りして答える構成にします。見出しと導入で要点を伝え、具体例を入れると理解しやすくなります。画像・動画は目的に合わせて最適化します。
テスト・検証
表示・動作確認はブラウザ・端末を横断して行います。リンク切れ、フォーム送信、読み込み速度、SEOの基本設定をチェックします。ユーザーテストで実際の使い勝手を確かめると安心です。
公開・運用開始
サーバーへのアップロード、DNS設定、SSL導入を行い、公開後はアクセス解析で効果を測ります。定期的なバックアップと更新計画を立て、改善サイクルを回してください。
Web制作を成功させるポイント
1. 目的とターゲットを最初に決める
制作の出発点は「何のために作るか」と「誰に届けるか」です。具体的な例を挙げると、主な来訪者を「25〜35歳の働く女性」「新規顧客」「既存会員」などに分け、各グループ向けの優先表示や導線を決めます。優先順位を決めると、デザインやコンテンツの判断が速くなります。
2. コミュニケーションを明確にする
制作会社や社内の担当者と定期的に進捗を共有します。週1回の短いミーティングや、決定事項をまとめた議事録を残すだけで認識のズレを減らせます。ワイヤーやデザイン案は「承認」ルールを設け、誰が最終決定するかを明確にしてください。
3. スケジュールと予算に余裕を持つ
想定外の変更や修正は必ず発生します。バッファ期間を設け、重要な納期(キャンペーン開始日など)は逆算して余裕を作ります。費用も作業ごとに見積もりを分けておくと、追加工数が発生した時に対応しやすくなります。
4. テストと検証を徹底する
リリース前は、表示崩れやフォーム送信、動作確認を実際の端末で必ず試してください。テスト項目をリスト化し、誰がどの項目を確認したかを残します。ステージング環境で本番に近い状態を確認すると安心です。
5. 変更管理と運用を考える
公開後の更新手順を決め、担当者と権限を明確にします。コンテンツ更新の手順書やバックアップ、公開前のチェックリストがあると、安全に運用できます。小さな改善を継続することで、長期的に効果が出ます。
Web制作の工程別・期間の目安
各工程の標準的な期間と、規模別の目安を分かりやすく説明します。実際の所要時間は内容や承認の速さで変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
企画・要件定義(小規模:1〜2週間/大規模:4〜8週間)
目的やターゲット、必要な機能を整理します。例えば会社紹介のサイトならページ数が少なく短期間で済みますが、ECや会員機能がある場合は仕様を詰めるのに時間がかかります。
設計・デザイン(2〜4週間)
ワイヤーフレームとビジュアルデザインを作ります。ページ数やデザイン案の数、修正回数で期間が変わります。レスポンシブ対応やCI(企業デザイン)との調整も考慮してください。
実装・コーディング(2〜4週間)
HTML/CSS/JavaScriptやCMS組み込みを行います。外部システム連携や複雑な機能があると延びます。並行してコンテンツ(文章や画像)を準備すると効率が上がります。
テスト・公開(約1週間)
動作確認、表示チェック、リンク確認、入力フォームの検証を行います。ステージングでの最終確認後にDNS切替や公開準備を進めます。
全体の目安と注意点
小〜中規模のサイトは一般的に2〜3ヶ月で完了します。大規模案件は6ヶ月以上かかることがあります。レビューの遅れや素材未準備が一番の遅延要因なので、早めの決定と素材提出を心がけるとよいです。
スケジュール短縮のコツ
事前に優先順位を決め、必須機能に集中します。テンプレートや既存モジュールを活用し、レビューは定期的に行うと手戻りが減ります。余裕を持ったスケジュールを組むのが安全です。
まとめ
Web制作は「目的設定」→「設計」→「デザイン」→「実装」→「テスト」→「公開」という流れが基本です。本章では、各工程の要点と実務で使えるチェックリストを丁寧にまとめます。
- 目的設定:誰に、何を伝えたいかを明確にします。例:新商品を知ってもらう、問い合わせを増やす。
- 設計:情報の構造と導線を作ります。サイトマップやワイヤーフレームで確認します。
- デザイン:ブランドや見やすさを重視します。色や余白、ボタンの配置を意識します。
- 実装:コーディングやCMS設定を行います。スマホ表示を必ずチェックします。
- テスト:リンク、表示速度、入力フォームの動作を確認します。想定ユーザーでの操作も試します。
- 公開・運用:公開後は解析で効果を測り改善を繰り返します。更新スケジュールを決めておくと安心です。
簡単なチェックリスト
– 目的が明確か
– 重要なページへ3クリック以内で到達できるか
– スマホで見やすいか
– フォームが正常に送信されるか
– 分析ツールが設置されているか
最後に、計画を小さなステップに分けて進めると失敗を減らせます。丁寧に確認しながら進めてください。