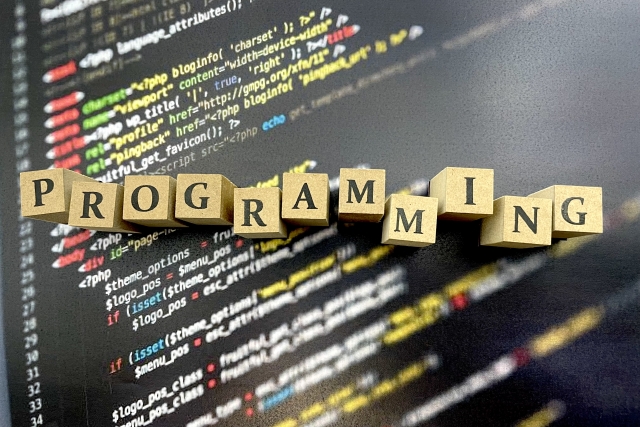はじめに
この記事の目的
この記事は、Webサイト制作の流れと進め方を分かりやすく解説します。企画から設計、デザイン制作、実装、公開、運用・改善まで順を追って説明します。初心者の方でも実務担当者でも参考になるように、具体例を交えて進め方を示します。
誰に向いているか
- これからサイトを作る個人や小規模事業者
- 担当者になったが全体像をつかみたい方
- 制作会社と円滑に進めたい発注者
本記事で学べること
- 各段階でやるべきことと優先順位
- 実務で役立つチェックポイントと具体例(例:ワイヤーフレーム、コンテンツ設計)
- 公開後に見るべき指標と改善の進め方
読み方のコツ
まずは全体の流れを把握してください。各章で具体的な手順や注意点を示しますので、自分の状況に合わせて取り入れてください。小さなサイトから始める場合は、企画とコンテンツをしっかり固めることが成功の近道です。
企画段階
目的の明確化
Webサイト制作はまず目的をはっきりさせます。例えば「商品の購入を増やす」「問い合わせを増やす」「ブランド認知を高める」などです。目的が決まると、評価指標(KPI)も決めやすくなります。例:月間CV(購入・問い合わせ)数、直帰率、滞在時間。
ターゲット分析
誰に向けて作るか具体的に描きます。年齢層、性別、興味関心、Webの利用習慣などを想像してください。ペルソナ(代表的な利用者像)を1〜3つ作ると伝わりやすくなります。例:30代子育て中の主婦、週に1回スマホで買い物をする。
競合調査
同じ分野のサイトを3〜5件調べます。良い点・悪い点、価格帯、導線(購入までの流れ)をメモします。真似るだけでなく、自分の強みを活かす改善点を見つけます。
要件定義と優先順位
必須機能(例:カート、問い合わせフォーム、ブログ)とあれば良い機能を分けます。優先順位を付けると、予算や期間に応じて段階的に実装できます。
コンテンツ構成(サイトマップ)
トップページ、主要ページ(商品一覧、商品詳細、会社情報、問い合わせ)を決め、簡単なサイトマップを作ります。導線を意識して、ユーザーが迷わない構成にします。
スケジュールと予算
制作期間、マイルストーン、予算上限を明記します。余裕のあるバッファを設けるとトラブルに強くなります。
簡単なチェックリスト
- 目的(KPI)を決めたか
- ペルソナを作ったか
- 競合の良し悪しを整理したか
- 必須機能と優先順位を決めたか
- サイトマップと予算・スケジュールを用意したか
これらを揃えると、設計段階へスムーズに進めます。
設計段階
概要
設計段階では、サイトの骨組みを決めます。サイトマップやワイヤーフレームを作成し、ページの役割や導線を明確にします。 UX設計やコンテンツ企画、システム選定もこの段階で行います。
サイトマップ作成
まず必要なページを洗い出します。例:トップ、会社情報、サービス、導入事例、ブログ、FAQ、お問い合わせ。ユーザーの目的(情報収集、購入、問い合わせ)を想定し、優先度をつけて階層を整理します。重要なページはトップから2クリック以内に届くようにします。
ワイヤーフレーム
低解像度の設計図を作ります。紙スケッチや簡単なツールでヘッダー、メイン、サイド、CTAの配置を決めます。例として、ファーストビューに訴求文と行動ボタンを置くと離脱を減らせます。ユーザーテストで簡単に修正できるようにします。
UX設計
ユーザージャーニーを描き、想定する人物像(ペルソナ)に沿って導線を最適化します。フォームは項目を絞り、入力の負担を減らします。モバイル優先で考えると使いやすさが上がります。
システム設計
CMSを使うか静的生成にするかを決めます。更新頻度や将来の拡張性、予算を基準に選びます。画像や動画の扱い、パフォーマンス対策もここで検討します。
コンテンツ企画
各ページの目的と掲載コンテンツを明確にします。見出し案、リード文、必要な画像や事例をリスト化し、制作スケジュールを作成します。
チェックリスト
- サイトマップ確定
- ワイヤーフレーム作成
- ペルソナとジャーニー定義
- 技術選定(CMS等)
- ページごとのコンテンツ案
- レスポンシブと読み込み速度の確認
デザイン制作
デザインコンセプトの策定
目的とターゲットを明確にし、伝えたい印象(親しみやすさ、信頼感、先進性など)を決めます。参考になる既存サイトや色見本を集め、ムードボードを作ると方向性がブレません。
素材の準備
写真、イラスト、アイコン、ロゴ、テキストを整理します。画質や使用許諾を確認し、ファイル名やフォルダで管理すると効率的です。例:CTA用のボタン画像、サービス説明の図解。
デザインカンプの作成
ワイヤーフレームから高解像度のカンプを作ります。トップページ、下層ページ、スマホ表示の主要パターンを用意します。色やフォント、間隔(余白)を統一し、視線の流れを意識して配置します。
レスポンシブとアクセシビリティ
スマホ・タブレットでの見え方を確認し、文字サイズやボタンのタップ領域を確保します。色のコントラストをチェックして、読みやすさを優先します。
レビューと引き渡し
関係者の意見を集めて調整します。変更履歴を残し、仕様書(フォント、カラー、余白、画像サイズなど)を添えて開発チームに引き渡します。フィードバックを受けて再度修正し、完成度を高めます。
実装段階
開発環境の準備
ローカル環境とリポジトリを用意します。Gitでブランチ運用を決め、依存関係はパッケージマネージャで管理します。例: Node.jsならpackage.jsonでライブラリを固定します。
フロントエンド実装
デザインをHTMLとCSSに変換します。まずは静的なマークアップを作り、次にレスポンシブ対応を行います。コンポーネント単位で作ると再利用しやすくなります。JavaScriptは必要最低限にして、フォームやモーダルなどの動作を確実にします。
バックエンド実装
APIやデータベースの設計に基づき、ルーティングとデータ処理を実装します。認証や入力チェックは早めに組み込みます。例: ユーザー登録時はメール重複チェックとパスワードのハッシュ化を行います。
テスト
単体テストで関数の動作を確認し、結合テストでAPIとフロントを合わせます。手動での受け入れテストも行い、主要な操作フローを人が確認します。バグは小さいうちに潰しましょう。
デプロイ準備
環境変数やビルドスクリプトを整え、ステージング環境で最終確認します。CIを使えばビルドとテストを自動化できます。デプロイ後はログを監視して問題を早く検知します。
運用を見据えた注意点
パフォーマンス対策(画像の最適化、キャッシュ設定)、セキュリティ(入力のサニタイズ、HTTPSの適用)を実装時に考慮してください。コードレビューとドキュメント作成で保守性を高めます。
公開段階
Webサイトをサーバーにアップロードし、一般公開する段階です。ここでは実際の手順と注意点を分かりやすく説明します。
サーバーへのアップロード
まず公開先サーバーを準備します。レンタルサーバーやクラウドのどちらでも構いません。ファイル転送はFTP/SFTPやGitを使います。例:FTPクライアント(FileZilla)で直接アップロード、あるいはGitHubから自動で反映する仕組み(GitHub Actionsなど)を使うと作業が楽になります。アップロード後はファイル権限や環境変数を確認してください。
DNSの設定
ドメイン管理画面でDNSレコードを設定します。AレコードはサーバーのIPを指し、CNAMEは別名を指します。設定後、反映まで数分〜72時間かかることがあります(DNS伝播)。メールを使う場合はMXレコードも忘れずに設定してください。
SSL(HTTPS)設定
通信を暗号化するためにSSLを導入します。無料のLet’s Encryptを使えば自動更新も可能です。必ずHTTPからHTTPSへリダイレクトする設定をしてください。
本番での確認項目
表示崩れ、リンク切れ、フォーム送信、画像の読み込み、スマホ表示、ページ速度、404ページの確認を行います。外部サービス(メール送信や決済)の動作も必ずテストしてください。
公開手順の例(簡易チェックリスト)
1) 最終バックアップを取得
2) ファイルをアップロード
3) DNS・SSLを設定
4) 本番で動作確認
5) 公開の告知
監視と障害対応
公開後はアクセスログやエラーログを監視します。簡単な監視(死活監視)やアラートを設定すると早く気づけます。問題が出たらバックアップから元に戻す手順を準備しておくと安心です。
注意点:CDNやキャッシュの設定で古い情報が表示されることがあります。公開直後はキャッシュをクリアして確認してください。
運用・改善
モニタリングと指標
公開後はまずアクセス状況を定期確認します。ページビュー、滞在時間、直帰率などを見て、どのページが読まれているか把握します。例えば、特定記事の滞在時間が短ければ本文の導入を見直します。
コンテンツの更新
情報が古くなったら速やかに更新します。商品情報や価格、連絡先は特に優先度が高いです。季節ごとの特集やFAQ追加など、具体的な更新案を月一回の目標にすると続けやすいです。
ユーザーの声を活かす
お問い合わせやサイト内のアンケート、コメントを定期的に集めて分類します。改善案は小さな変更から試し、効果が出れば拡大します。
A/Bテストと仮説検証
見出しやCTA(行動を促すボタン)の文言や配置を変えて、どちらが反応が良いか試します。小さな仮説を立てて短期間で検証すると効率的です。
保守と安全対策
定期バックアップ、プラグインやソフトの更新、表示速度のチェックを怠らないでください。問題が起きた時に元に戻せる体制が大切です。
運用スケジュール例
・週次:アクセス確認、簡単な修正
・月次:コンテンツ更新、ユーザー声の反映
・四半期:大きな改善計画と効果測定
ちょっとした改善を積み重ねることで、サイトの価値は確実に高まります。小さな変化を続けて、ユーザーにとって使いやすいサイトを目指しましょう。
SEO対策の重要性
なぜSEOが必要か
検索エンジンからの自然流入は費用対効果が高いです。広告に頼らず長期的に訪問者を集められます。例えば、地域のパン屋なら「手作りパン 渋谷」といった検索で上位表示されれば来店につながります。
キーワード選定のコツ
ユーザーの意図(探している情報や目的)を考えてキーワードを選びます。短い語(例:「パン」)より具体的な語(例:「朝食向け 天然酵母パン」)で競争が少なく成果を出しやすいです。無料ツールや検索候補を参考にします。
自然な文脈での挿入
タイトル、見出し、冒頭文、メタディスクリプションに自然にキーワードを入れます。文章を読んだ人に違和感が出ないように書き、無理に詰め込まないことが重要です。商品説明やブログ本文で例を示すと分かりやすくなります。
技術的な基本
ページの表示速度、モバイル対応、適切なURLやalt属性など、技術面も評価に影響します。簡単な対応として画像を圧縮し、レスポンシブデザインを採用します。
コンテンツの質と更新
役に立つ情報を丁寧に書き、定期的に更新します。古い情報は見直して最新の状態にすることで検索評価が上がりやすいです。内部リンクで関連ページをつなげます。
効果測定と改善
Google Search Consoleやアクセス解析でクリック数や表示回数、流入経路を確認します。データに基づいてタイトルや本文を改善し、効果が出るまで繰り返し調整します。