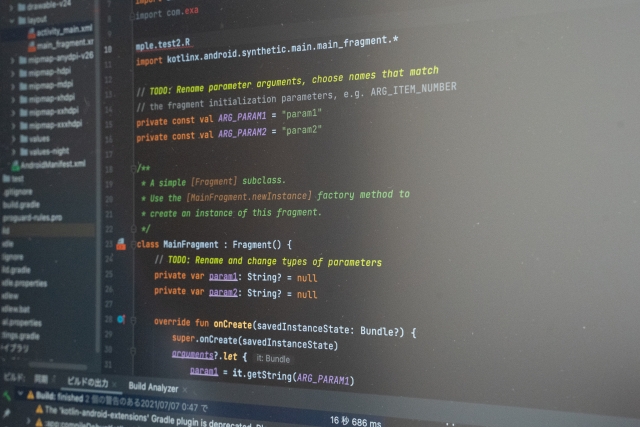はじめに
概要
本ドキュメントは、サイトリニューアルにおけるRFP(提案依頼書)について、その基本的な定義、役割、作成手順、制作会社の選定方法、及び関連するサポートリソースをまとめたものです。企業がWebサイトのリニューアルを外部に依頼する際に必要な情報を体系的に解説します。
対象読者
- Web担当者、経営者、プロジェクトマネージャーなど、外注先を選ぶ立場の方
- 初めてRFPを作る方や、既存の方法を見直したい方
本ドキュメントの目的
- RFPの目的と効果を理解していただくこと
- 実務で使える手順とチェックポイントを提供すること
- 制作会社との認識合わせをスムーズにすること
使い方
次章でRFPの基本を説明し、続けて作成フロー、選定基準、テンプレートへと進みます。実務に即した例を交え、段階的に読み進められる構成にしています。必要な情報を見つけやすいように章ごとに整理しています。
この先で具体的な記載項目や注意点を丁寧に解説しますので、まずは本ドキュメントの全体像を把握してから読み進めてください。
RFPとは何か
定義と目的
RFP(Request for Proposal)は「提案依頼書」です。発注者がプロジェクトの目的や要望をまとめ、複数の制作会社やベンダーに具体的な提案を求める公式な文書です。提案内容を比較して最適なパートナーを選ぶことが目的です。
RFPに含める主な項目(具体例付き)
- 目的・背景:新しい顧客獲得のためにサイトを見直したい、など
- 範囲・要件:ページ数、機能(フォーム、会員機能、レスポンシブ対応)
- 自社の現状と課題:現行サイトの流入減少や更新負荷が高い、など
- 予算と納期:概算予算、希望納期(例:6か月以内)
- 成果物のイメージ:ワイヤーフレーム、デザイン案、実装、テスト
- 評価基準:技術力、実績、価格、スケジュール遵守
ホームページリニューアルでの使い方
RFPを出すことで制作会社は要求を正確に把握できます。仕様が明確だと見積もりや提案の質が上がり、後の齟齬を減らせます。例として、目標KPI(問い合わせ数を月間30件に)を示すと提案が具体化します。
RFPと似た書類の違い
- RFI(情報提供依頼):まず情報を集める段階で使います。簡易的です。
- RFQ(見積依頼):仕様が確定していて価格を求めるときに使います。
RFPは要件と期待を伝え、最良の提案を受け取るための重要なツールです。
RFPの役割と重要性
ホームページのリニューアルを成功させるには、目的に合った提案を受け取り、適切な制作会社を選ぶことが不可欠です。RFP(提案依頼書)は、そのための設計図になります。
ホームページは「企業の顔」
ホームページは外部に見せる最初の窓口です。第一印象や信頼感、ブランドイメージに直結します。ユーザーが求める情報にすぐたどり着ける設計や、購入や問い合わせにつながる導線設計は売上や問い合わせ数に影響します。
RFPが果たす主な役割
- 要件を明確にする:ターゲット、目的、KPI(例:CVR、滞在時間)、必須機能を示すと提案の質が高まります。
- 比較可能な提案を引き出す:同じ基準で複数社を評価できます。
- 期待値を共有する:納期、予算、検収基準を事前に伝えることで認識齟齬を防ぎます。
- リスク排除と交渉力の向上:不明点が少ないほど見積りのばらつきが減り、コストパフォーマンスが改善します。
具体例
ECサイトのリニューアルなら「月間CVを20%改善」や「決済フロー短縮」など具体的な目標を示すと、制作会社は最適な施策(UI改善、A/Bテストなど)を提案しやすくなります。
最後に
RFPは単なる書類ではなく、社内外のコミュニケーションツールです。丁寧に作れば制作の質と選定の透明性が高まり、結果的に費用対効果が向上します。
RFP作成の手順と注意点
準備:目的と現状整理
最初にリニューアルの目的を明確にします。例:問い合わせ数を増やす、操作性を改善する、ブランドイメージを刷新する。現状の課題(アクセス解析やユーザーフィードバック)と成功指標(KPI)を具体化してください。現行サイトのページ構成や運用ルール、既存の資産(画像・テキスト・データベース)も整理します。
要件のまとめ(機能・非機能)
機能要件は具体的に書きます。たとえば、会員登録、検索機能、予約機能など。非機能要件は性能やセキュリティ、対応ブラウザ、アクセシビリティ基準を含めます。優先度を「必須」「希望」「参考」に分けるとベンダーが見積りを出しやすくなります。
予算とスケジュールの明記
概算予算帯(例:300万〜500万)と決定・開発・公開のマイルストーンを示します。選考スケジュール(質問受付期限、提案提出期限、選定日)も明確にしてください。予算は余裕を持たせ、追加要件発生時の対応方針も記載すると安心です。
提出物と評価基準
提出してほしい資料を列挙します(提案書、見積書、制作スケジュール、実績例、技術構成)。評価基準は重み付けをすると透明性が増します。例:技術力40%、実績30%、価格20%、コミュニケーション10%。
リニューアル時の取り扱いとユーザー影響の注意点
公開タイミングや段階公開、リダイレクト設定、既存コンテンツの移行計画を明記してください。失敗するとユーザーに混乱を招いたりSEOに悪影響が出ます。公開前にステージング環境で十分な検証とユーザーテストを行いましょう。
リスク管理と連絡体制
想定されるリスク(スケジュール遅延、要件増加、外部連携の不具合)と対応フローを用意します。連絡窓口、決裁者、週次ミーティングの頻度も記載してください。
チェックリスト(簡易)
- 目的とKPIが明確か
- 必須要件と優先度を定義したか
- 予算とスケジュールを提示したか
- 提出物と評価基準を示したか
- 移行・公開手順とテスト計画があるか
- リスクと連絡体制を決めたか
これらを揃えると、ベンダーの提案精度が上がり、プロジェクトの進行がスムーズになります。必要に応じて社内で合意を取り、関係者全員が同じ認識を持つことを心がけてください。
制作会社の選定とその後のプロセス
候補企業を比較するポイント
- 実績:同業種や似た規模のサイト制作経験を確認します。例えばコーポレートサイトやECの事例を実際に見て、成果や課題をチェックします。
- 技術力:CMS、レスポンシブ対応、パフォーマンス改善の実績を見ます。使う技術や保守体制を具体的に聞きます。
- 対応範囲:デザイン、開発、SEO、運用支援まで含むかを確認します。範囲外は別途コストがかかります。
- 柔軟性と提案力:問題提起と改善提案の質で判断します。具体的な代替案を示せるかが重要です。
RFP提出後の流れと確認事項
提案書と見積書を受け取ったら、要件が反映されているか、納期とマイルストーン、保守費用を細かく確認します。質問会やプレゼンでコミュニケーションの取りやすさを確かめます。
発注側の力量とコミュニケーションコスト
制作会社は発注側の情報整理能力を見ます。要件の曖昧さが多いと仕様調整に時間がかかりコスト増になります。担当者の決裁フローや回答速度も事前に整えておくとスムーズです。
制作中の管理と品質チェック
定期的なレビューと検証環境での確認を設定します。デザインの合意、機能テスト、アクセシビリティや表示確認を段階的に行います。チェックリストを共有すると抜けが減ります。
リニューアル後の効果測定と改善
アクセス解析ツールで流入・行動・コンバージョンを計測します。ヒートマップやABテストで仮説検証し、優先順位をつけて改善を繰り返します。制作会社と運用フェーズでの連携体制を契約で明示しておくと安心です。
RFPテンプレートとサポートリソース
無料テンプレートとサンプル
RFP作成が初めての方には、無料で使えるテンプレートや完成例が便利です。多くの制作会社や業界団体が公開しています。例:目的(問い合わせ増加、ブランド刷新)、予算、スケジュール、対象ユーザー、必要な機能、運用体制、審査基準を項目として用意すると良いです。実際のサンプルを参考に、記入例を真似してみてください。
テンプレートの使い方(手順と注意点)
- 自社の目的を先に明確化します(例:月間問合せ数を2倍にする)。
- テンプレートの不要項目は削除し、固有の条件を追記します。
- 技術的な詳細が分からなければ「要相談」と記載して外注先と詰めます。
- 添付資料(現状サイトのアクセス数、ブランドガイド、ワイヤーフレーム)を用意します。
注意点:曖昧な要望は差し戻しの原因になります。具体例を入れてください。
サポートリソース(相談窓口と学習)
- 専門家によるコンサルティングやレビューサービス。企画段階で第三者の目を入れると精度が上がります。
- ウェビナーやオンライン講座でRFPの書き方や発注後の進め方を学べます。
- Q&Aフォーラムや制作会社の問合せ窓口で実務的な相談が可能です。
実務での活用方法
テンプレートで下書きを作り、社内の関係者に回覧してフィードバックを集めます。その後、候補の制作会社に共有して見積りと提案を比較してください。必要なら専門家のレビューを受け、最終版を作成して公募に進みます。
最後に
テンプレートは土台です。自社の目的と制約に合わせて調整し、対話を重ねることで使いやすいRFPになります。