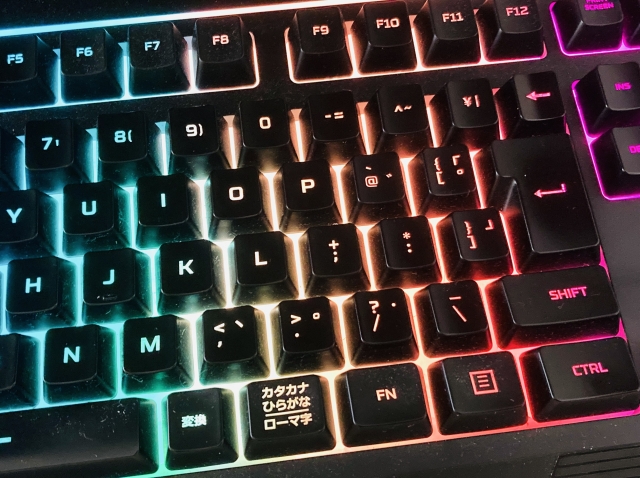はじめに
目的
この章では、金継ぎの技術をアクセサリー作りに応用する「金継ぎアクセサリー」についての導入をします。初心者の方でも取り組みやすいように、必要な材料や手順、楽しみ方をこれからの章で丁寧に解説します。
この記事で分かること
- 金継ぎアクセサリーとは何かの概略
- 使える素材や基本材料の種類
- 初心者向けの作り方の流れ
- 市販キットやワークショップの選び方
- サステナブルな魅力と保管のコツ
誰に向けた記事か
ハンドメイドが好きな方、器の修理に興味がある方、廃材を活かしたアクセサリー作りを始めたい方に向けています。専門知識がなくても分かるように、具体例を交えて説明します。
本記事の進め方
第2章以降で具体的な素材や手順を順に説明します。まずは全体像をつかんでいただき、必要に応じて各章を詳しく読み進めてください。写真やキットの紹介も交え、実際に作るイメージを持てるようにします。
注意点
作業中は割れた陶磁器の破片で手を切ることがあります。手袋や保護具を用意し、換気の良い場所で作業してください。安全第一で楽しみましょう。
金継ぎアクセサリーとは?
金継ぎの基本
金継ぎは、壊れた陶器を漆で接着し、金粉や金箔で継ぎ目を装飾する日本の伝統技術です。元は器の修理法ですが、その美しい“継ぎ目”を意匠に活かし、アクセサリーに仕立てる動きが広がっています。
どんな素材が使われるか
割れた陶片のほか、シーグラス(海で磨かれたガラス)、天然石、貝殻、金属片などを素材に使います。小さな欠片でも個性豊かなピースになり、イヤリングやペンダント、ブローチなどに加工できます。
特徴と魅力
修理の跡を隠すのではなく強調するため、世界に一つだけの表情が生まれます。壊れたものを再生するという点でエコでもあり、素材の歴史や物語を身につけられる点が魅力です。
初めての方への注意点
漆にアレルギーが出る人がいるため、皮膚に直接触れる部分は金属やレジンで封止する方法もあります。日常使いの際は強い衝撃や長時間の水濡れを避け、やさしく扱ってください。
金継ぎアクセサリーに使える素材
金継ぎアクセサリーは、割れや欠けを美しく生かすことで唯一無二の表情を作れます。ここでは代表的な素材と、扱うときのポイントをやさしくまとめます。
陶器・陶片(有田焼・伊万里焼・唐津焼など)
- 特徴:模様や釉薬の色味が豊富で、和風からモダンまで幅広く合います。
- ポイント:厚みや重さを確かめて、ピアスには薄手の陶片を選びます。欠け面はやすりで滑らかに整え、接着剤ののりを良くします。
シーグラス(海で磨かれた曇りガラス)
- 特徴:柔らかな色合いと手触りが魅力。軽くて扱いやすいです。
- ポイント:穴あけや接着がしやすく、夏アクセサリーに向きます。光を受けると表情が変わる素材です。
天然石(誕生石やカラフルな石)
- 特徴:色や模様が個性的で高級感があります。
- ポイント:石の硬さや形に合わせた金具選びが重要です。衝撃に弱い石もあるので扱いに注意します。
貝殻・シェル
- 特徴:光沢や虹色の輝きがアクセントになります。
- ポイント:薄く割れやすいので、裏面を補強してから金継ぎすると丈夫になります。
アクセサリーパーツ(ピアス金具・イヤリング金具・台座など)
- 特徴:仕上がりの着け心地や耐久性を左右します。
- ポイント:素材の重さに合った金具を選び、接合部分は強度を確保して作ります。
素材同士を組み合わせると表現が広がります。色・質感・重さを意識して、身に着けやすいバランスを探してみてください。
金継ぎアクセサリー作りの基本材料
接着剤
金継ぎ風アクセサリーでは、合成漆や「新うるし」などの接着剤をよく使います。乾燥が早く扱いやすい合成漆は初心者向けです。一方で本物のうるしは強度や光沢が出ますが、アレルギーに注意が必要です。
金属粉(仕上げ材)
金粉は本格的な金継ぎの定番です。予算や雰囲気で真鍮粉やパール粉を使うと、金色以外の表現が楽しめます。粉の粒度で光り方が変わるので、小瓶で試してみてください。
ヤスリ・サンドペーパー
400番程度の紙ヤスリがあると、接着後の段差や余分な接着剤を整えやすいです。仕上げに細かい番手を使うと表面が滑らかになります。
筆と筆洗い液
細筆は金粉を置く作業や接着剤の塗布に必須です。天然毛・合成毛どちらでも使えます。筆洗い液は素材に合わせて選び、よく洗ってから保管してください。
本格的な材料(必要に応じて)
木粉・砥粉・黒粉・弁柄粉は、欠け部分の盛り土や着色に用います。簡易金継ぎでは省けることが多いので、最初は不要です。
その他小物
手袋、マスキングテープ、ピンセット、混練用のへらやスプーンは作業を楽にします。
安全のポイント
換気を良くし、手袋やマスクを使ってください。接着剤や粉末は肌や呼吸器に触れないよう注意しましょう。
金継ぎアクセサリーの作り方手順
以下は初心者向けの簡易金継ぎアクセサリーの基本手順です。丁寧に進めればきれいに仕上がります。
準備
- 素材例:天然石、シーグラス、陶片など。パーツ例:ピアス台、イヤリング台、ブローチ台。作業場は換気し、手袋とマスクを用意します。
手順(6ステップ)
- 素材選び
- 割れやすい部分がないか確認します。接着面が平らだと作業が楽です。
- パーツ選びと仮止め
- 金属パーツを置き位置で確認し、仮止めテープで固定します。
- 接着面の下処理
- 紙ヤスリ(#400〜600程度)で軽くこすり、ホコリを払います。表面を荒らすことで接着剤がなじみます。
- 接着
- 合成漆や新うるしを薄く塗り、パーツを押し付けます。はみ出した場合は布で軽く拭き取ります。
- 金属粉で装飾
- 漆が半乾き(触れて跡が残る程度)のときに金粉や金属色パウダーを置きます。筆で余分を落とします。
- 乾燥と仕上げ
- 完全に乾燥させてから余分な粉を払い、必要ならトップコートで保護します。接続金具を最終取り付けします。
コツと注意点
- 乾燥時間は素材や温度で変わります。焦らず十分に置いてください。
- はみ出しは乾く前に拭き取り、乾いた後はやすりで整えます。
- 小さな破片は使い道があるので保管すると良いです。
この手順を守れば初心者でも美しい金継ぎアクセサリーが作れます。ゆっくり丁寧に進めてください。
金継ぎアクセサリーキット・ワークショップ
キットに含まれるもの
初心者向けのキットは、シーグラスや天然石などの素材、合成漆(扱いやすいタイプ)、金属粉(真鍮や金色粉)、接着剤、筆、研磨紙、ピンセット、金具、取扱説明書が一式になっています。箱を開けるとすぐ作業できるように必要最小限が揃っています。
キットの選び方のポイント
説明書が丁寧にあるかを確認してください。写真や手順図があると失敗が少なくなります。金粉は本金粉より扱いやすい合成のものが入ることが多く、初めてなら十分です。工具類が安価すぎないか、替えの筆や接着剤が用意できるかも見ておくと安心です。
ワークショップの種類と特徴
半日〜1日で学べる体験教室や、全工程を学ぶ連続講座、オンライン講座があります。対面では講師が直接手直しやコツを教えてくれるため、初心者は参加をおすすめします。少人数制だと質問しやすく作業も丁寧に進められます。
持ち込み素材と注意点
多くの教室は持ち込みに対応します。割れた陶片や自分で集めたシーグラスを使う場合は事前に相談してください。素材の大きさや表面状態によって糊や下地処理が変わるため、講師の指示に従って準備しましょう。汚れや砂は必ず落としてから持参してください。
料金と持ち物
キットは2,000〜10,000円程度、ワークショップの参加費は3,000〜8,000円が目安です。エプロン、布、持ち帰り用の箱を持参すると便利です。乾燥時間や硬化に数時間〜数日を要する場合があるため、仕上がりの受け取り方法を確認してください。
最後に
初心者向けのキットと講座は手順が分かりやすく、失敗を減らして楽しめます。まずは簡単なセットで練習し、慣れてきたら素材や金粉をグレードアップすると良いでしょう。
金継ぎアクセサリーの魅力とSDGs
概要
金継ぎアクセサリーは、割れた陶器やシーグラス、金属パーツなどの廃材を生かして作るアクセサリーです。壊れたものに新しい価値を添える習慣は、日本の「もったいない」精神とクラフトマンシップが結び付き、見た目にも心地よい独特の美しさを生み出します。
環境への貢献
素材を捨てずに再利用することで、廃棄物の削減に役立ちます。たとえば、割れた器をそのまま埋めるのではなくピアスやペンダントに仕立てると、焼き物の寿命を延ばせます。資源の新規採掘や大量生産を抑える効果も期待できます。
社会・経済的な利点
地元の陶芸家や海辺で拾ったシーグラスを使うと、地域の小さな経済にもつながります。ワークショップや販売を通じて手仕事の技術を伝え、職人やクリエイターの収入源になります。個人が始めやすいハンドメイドのため、参入障壁が低い点も魅力です。
文化と美意識の融合
金継ぎは欠けを隠すのではなく美として尊ぶ技法です。その考え方がアクセサリーにも反映され、ひとつひとつ異なる表情が生まれます。持ち主のストーリーが刻まれた一点物としての価値が高まります。
実践のヒント
・素材の由来を明記すると、購入者にとっての価値が伝わります。たとえば「地元の窯で割れた器を再利用」など。
・修理や補強の際は耐久性を意識して、長く使える仕上げを心がけてください。
・ワークショップで学び合うことで、地域の循環型ものづくりを広げられます。
金継ぎアクセサリーは、捨てる文化を見直し、小さな循環を生み出す実践です。素材の物語を大切にすることで、環境面と社会面の双方に良い影響を与えます。
まとめ:金継ぎアクセサリーにおすすめの材料リスト
おすすめ材料一覧
- 割れた陶器・陶片:模様や色が個性的な破片を選ぶとアクセントになります。
- シーグラス:角が取れていて扱いやすく、ビーチで拾ったものは風合いがあります。
- 天然石:小さめのものはそのまま使えます。色合いで印象を変えられます。
- 貝殻:薄くて軽いのでピアスに向きます。光沢が美しいです。
- アクセサリー金具:台座、ピアス・イヤリング金具、チェーン、丸カンなど。
- 合成漆(新うるし):扱いやすくアレルギーの心配が少ないタイプを選びます。
- 金属粉:金粉、真鍮粉、パール粉など。接着面を飾るのに使います。
- 紙ヤスリ:#240〜#600程度を揃えると下処理が楽です。
- 筆・筆洗い液:金粉を塗る細い筆と、汚れを落とすための筆洗い液。
選び方のポイント
- 軽さを優先する:長時間身につけるなら軽い素材を選びます。
- 安全性を考える:合成漆や金属粉は、成分表示を確認して安全なものを選びます。
- 大きさのバランス:顔周りに使うなら小ぶり、胸元ならやや大きめが映えます。
初心者向けスターターキット例(おすすめセット)
- 陶片2〜3点、シーグラス数個、台座・ピアス金具セット、合成漆小瓶、金粉少量、紙ヤスリセット(3種)、細筆。
取り扱いと保管の注意
- 金属粉や漆は直接吸わないよう換気して作業してください。
- 完成品は柔らかい布で拭き、湿気の少ない場所で保管します。
これらを揃えれば初心者でも手軽にオリジナルの金継ぎアクセサリー作りを楽しめます。必要に応じて少しずつ材料を増やしていくと良いです。