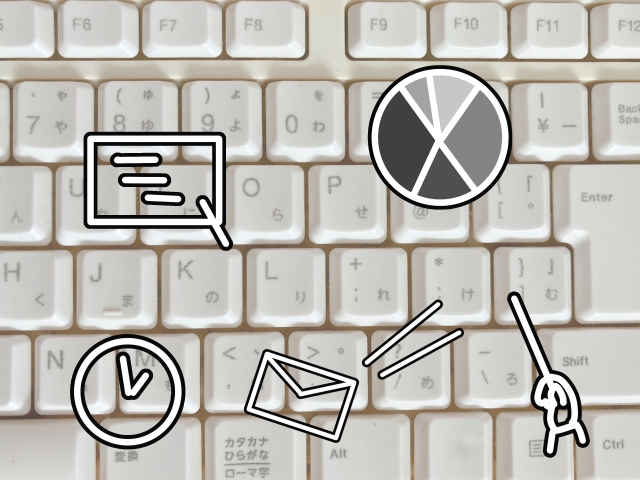はじめに
概要
本記事はAWSクラウド移行戦略の「7R」フレームワークをやさしく解説します。7Rは、オンプレミスや他クラウドからAWSへ移すときの代表的な7つの選択肢を示します。各手法の特徴、選び方、移行手順や起こり得る課題、実例まで網羅的に扱います。
対象読者
- クラウド移行を検討する技術担当者や意思決定者
- これから移行計画を立てるプロジェクトマネージャー
- クラウドの基本を学びたいエンジニア
具体例を交えて説明しますので、専門用語が苦手でも読み進めやすくしています。
本章の目的
この「はじめに」では、本記事の全体像と読み方を提示します。まず7Rの意義を理解し、次章以降で各手法を深掘りしてください。
この記事の構成と読み方
- 第2章で7Rの全体像を示します。まずここを読めば全体が把握できます。
- 第3章以降で各手法の詳細、実務上の注意点を説明します。
- 具体的な移行手順や事例は第5章・第6章で扱います。
注意点
用語は可能な限り平易に説明します。具体的な判断には現場の要件(性能、コスト、運用体制)を必ず考慮してください。
AWS「7R」とは何か
概要
AWSの「7R」とは、オンプレミスや他クラウドからAWSへ移行する際に選べる7つの基本戦略を整理した枠組みです。各手法は英語がRで始まる単語に由来し、目的や制約に応じて使い分けます。実務の判断材料として広く使われています。
7つのRの簡単な説明
- Rehost(リホスト): 既存のサーバーをそのままクラウドへ移す「リフト&シフト」です。短期間で移行したい場合に使います。
- Replatform(リプラットフォーム): 大枠は残しつつ、一部をクラウド向けのマネージドサービスに置き換えます。例: データベースをRDSへ移す。
- Refactor(リファクタ): アプリを設計から見直してクラウド向けに再構築します。パフォーマンスや拡張性を重視する場合に選びます。
- Relocate(リロケート): アプリやVMを最小の変更で別の運用基盤へ移します。ツールを使って移行するケースが多いです。
- Repurchase(リパーチェス): 現行システムを廃止して、SaaSや別製品を購入して置き換えます。例: 自社ERPをクラウドサービスに切替。
- Retire(リタイア): 使われていないサービスを廃止してコストを削減します。
- Retain(リテイン): 今は現状維持し、後で再検討する方針です。移行の優先順位付けで使います。
実務での使い方(ヒント)
目的、コスト、工期、運用スキルを軸に判断します。短期で成果を出したいならRehost、長期の最適化を狙うならRefactorが有効です。各システムを個別に評価して、混在させることが現実的です。
7R各手法の詳細解説
Rehost(リホスト)
既存のサーバーやアプリをほぼそのままAWS上の仮想サーバーに移す方法です。改修をほとんど行わないため移行が早く、短期的にコストと作業を抑えられます。例:オンプレのWebサーバーをEC2にコピーして運用を続ける。注意点はクラウド固有の利点(自動スケールやマネージドサービス)を十分に活かせない点です。
Replatform(リプラットフォーム)
一部だけをクラウド向けに最適化する方法です。アプリの構成やミドルウェアを少し変更して、管理の手間を減らします。例:データベースをRDSに移す、コンテナ化してECSに載せる。手間は中程度で、運用負担を下げながら大きな改修は不要です。
Refactor(リファクタ)
コードや設計を大幅に見直し、クラウドネイティブな技術を使う方法です。マイクロサービス化やサーバーレス化で可用性や拡張性を高めます。例:バッチ処理をLambdaに置き換える。利点は長期的な運用コスト削減と柔軟性の向上ですが、開発コストと期間が大きくなります。
Relocate(リロケート)
仮想化環境そのものを丸ごとAWSに移す方法です。VMwareなどの環境をそのまま移行でき、改修不要で短期間に実行可能です。既存の設定を維持したい場合に有効です。
Repurchase(リパーチェス)
既存システムを廃止し、SaaSや商用パッケージに乗り換えます。例:社内の勤怠システムをSaaSに切り替える。運用は簡単になりますが、機能やカスタマイズの制約が出ることがあります。
Retire(リタイア)
不要なアプリやサービスを停止・削除する選択です。保守コストを即座に減らせます。まずは利用状況を確認して、本当に不要か判断します。
Retain(リテイン)
現状のまま維持する方法です。移行の優先度が低い、または移行リスクが高い場合に選びます。将来的な見直しを前提に、段階的に対応することが多いです。
各手法は目的や期間、コストのバランスで選びます。短期で確実に移すならRehostやRelocate、長期的な最適化を目指すならRefactorやRepurchaseが向きます。
7Rを選定する際のポイント・分類
はじめに
7Rは目的や手間の違いで大きく三つのグループに分かれます。ここでは実務で選定するときに見るべきポイントと、判定の流れをわかりやすく説明します。
三つのグループと特徴
- クラウド移行しない(Retire・Retain)
- 不要なシステムは廃止(Retire)。法規や稼働理由で残す場合は維持(Retain)。コスト削減やリスク低減が狙いです。
- クラウドリフト(Relocate・Rehost)
- 構成をほぼ変えずにインフラだけ移す方法です。短期間でリスク小、迅速に効果を出せます。
- クラウドシフト(Repurchase・Replatform・Refactor)
- 機能や構造を見直してクラウドの利点を活かします。開発コストはかかりますが、拡張性や運用効率が向上します。
選定の主な基準(チェックリスト)
- ビジネス重要度:停止での影響度を評価します。
- コスト:現在運用費と移行後の見込みを比較します。
- 技術的依存関係:他システムやデータの結びつきを確認します。
- 将来性:今後の拡張や機能追加の計画を考慮します。
- 運用負荷とスキル:運用チームの技術力と工数を合わせて判断します。
- セキュリティ・コンプライアンス:規制要件に適合するかを確認します。
判定の流れ(実務的ステップ)
- アセットの棚卸し:資産と依存関係を洗い出します。
- スコアリング:上の基準で点数化します。
- グルーピング:スコアに応じて三グループへ振り分けます。
- パイロット実施:代表的なシステムで移行を試します。
- 本格移行計画:影響範囲とロールバック策を含めて計画します。
実務上の注意点
利害関係者の合意を早めに取ること、短期効果と長期価値の両方を評価すること、コスト監視の仕組みを用意することが重要です。以上を踏まえ、目的に合った7Rを選んでください。
具体的な移行手順と課題
移行手順の全体フロー
- 現状評価:アプリ・データ量、依存関係、性能要件を洗い出します。
- 戦略決定:7Rのどれを採るか選び、優先順位を付けます。
- 設計・計画:移行スケジュール、リスク、ロールを明確にします。
- リハーサル:小規模でテスト移行を行い問題点を洗い出します。
- 実施:段階的に部分移行し、最終的に全面移行します。
準備と評価で重視する点
- 依存関係の可視化:連携するシステムを漏れなく特定します。
- 性能基準の設定:現行の応答時間やバッチ処理時間を記録します。
- 移行ウィンドウの確保:業務影響が少ない時間帯を選びます。
リハーサル(テスト移行)の進め方
- 本番に近い環境で一連の流れを確認します。
- ロールバック手順を必ず準備します。
- テストで見つかった問題は優先度を付けて修正します。
部分移行と全面移行の実務ポイント
- 先にリスクが低いモジュールを移すと安心です。
- データ同期は整合性を確認しながら段階的に行います。
- 切替時はモニタリングを強化し、早期に問題を検知します。
技術的課題と対策(例)
- 互換性:レガシーのOSやミドルウェアが動かない場合はリファクタやコンテナ化で対応します。
- パフォーマンス:負荷試験でボトルネックを特定し、リソース調整やキャッシュ導入で改善します。
- セキュリティ:アクセス制御や通信の暗号化を適用し、脆弱性スキャンを実施します。
非技術的課題と対策
- コスト管理:移行後の運用コスト見積りを行い、予算管理ルールを定めます。
- 運用体制:役割分担と手順書を整備し、運用担当に教育を行います。
- 社内合意:関係部門との定期的な報告で理解を得ます。
移行後の確認事項
- 後方互換性の検証とユーザー受け入れを行います。
- 運用手順を本番向けに最適化して完了とします。
7Rの実例・応用と最新トレンド
概要
近年はリロケート(仮想化環境ごとAWSへ移行)が注目されます。ご提示のとおり、提供形態の変化で選択肢が変わることもあるため、移行方式の再評価が重要です。一方で、リファクタやリプラットフォーム、リパーチェスなどのクラウドシフトは多くの企業で採用され、クラウドの価値を引き出しています。
実例紹介
- 小規模Webアプリ(リロケート): 仮想マシンをそのまま移して短期間で運用継続。移行コストを抑えつつダウンタイムを最小化できます。運用手順は従来と似るため導入障壁が低いです。
- 業務系システム(リプラットフォーム): ミドルウェアをクラウド向けに変えて性能改善。大幅なコード変更を避けつつスケール性を得られます。
- SaaS導入(リパーチェス): 自社で運用する代わりにSaaSを採用して運用負荷とコストを削減。機能要件とデータ移行の検討が鍵です。
- マイクロサービス化(リファクタ): コンテナやサーバーレスで分割し柔軟に拡張。初期コストと設計力が必要です。
選定の観点
現状の技術負債、将来的な拡張性、コスト構造、事業の優先度を総合的に評価します。短期的な可用性優先ならリロケート、長期的な運用効率と革新性を重視するならリファクタやリプラットフォームが向きます。
応用と最新トレンド(実務視点)
- ハイブリッド戦略: 一部をSaaS化し、コアだけをクラウドで最適化する選択が増えます。
- 自動化の活用: テストとデプロイの自動化でリファクタ後の運用負荷を下げます。
- コスト管理の重視: 移行後のコストを見える化し継続的に最適化します。
注意点
短期の利便性だけで決めず、運用体制やスキル、データ保護の要件を確認してください。移行は技術だけでなく組織の変化も伴いますので、関係者の合意と段階的な計画が成功の鍵です。
まとめ — 7R戦略を活用したAWS移行のベストプラクティス
要点の振り返り
7Rフレームワークは、移行対象ごとに最適な選択肢を整理する枠組みです。全てを一度に変えようとせず、業務への影響やコスト、リスクを基に優先順位を決めることが重要です。例として、稼働時間が短い開発環境はそのまま移す(Rehost)だけで労力を節約できますし、長期的に拡張したいサービスは設計を見直す(Refactor)価値があります。
実践ステップ(簡潔)
- 現状把握:資産一覧、依存関係、コストを可視化します。簡単な例はサーバー台帳を作ることです。
- 分類と優先度付け:業務重要度と移行難易度で優先度をつけます。
- 戦略決定と小さな実行:まずは影響の少ない領域で試験的に移行し、学びを得ます。
- 本格移行と最適化:監視や自動化を導入し、運用コストを下げます。
技術面・組織面での注意点
- 技術面:互換性やデータ移行の方法を事前に検証します(例:データベースの同期方法)。
- 組織面:関係者の合意、技術教育、運用体制の見直しを行います。コミュニケーションを怠ると予定通り進みません。
ベストプラクティスチェックリスト
- 小さな成果を早めに出す(早期の成功体験)
- コストとセキュリティを移行計画に組み込む
- 自動化と監視で運用負荷を下げる
- 定期的に戦略を見直す
最後に
移行は技術だけでなく、人とプロセスの変化でもあります。段階的に進め、得た知見を次に活かす姿勢が成功の鍵です。柔軟に戦略を選び、確実に実行していきましょう。