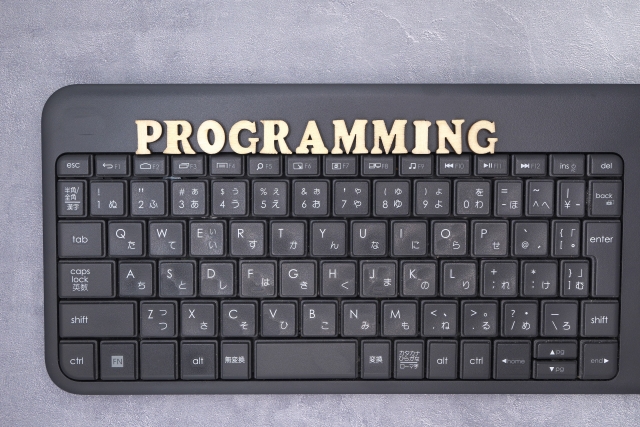はじめに
対象読者と目的
この章は、Webサイトのリニューアルを検討している担当者向けです。自社サイトの見直しを検討し始めた方、制作会社に依頼する前に準備をしたい方、現状の課題を整理したい方に向けて書いています。本記事は、目的の立て方から公開後の運用まで一連の流れをわかりやすく解説します。
このガイドの使い方
全7章で構成し、順を追って進めれば実務に役立ちます。第2章でリニューアルの基本を説明し、第3章で具体的な手順を紹介します。以降は注意点、制作期間、よくある失敗例と対策、最後に成功のポイントをまとめます。章ごとに必要なチェック項目や実例を載せるので、実務チェックリストとしても使えます。
リニューアルで期待できる効果(簡単に)
- ユーザーが情報を見つけやすくなり、問い合わせや購入が増える
- 管理しやすい仕組みにして運用コストを下げる
- デザインや表現でブランドの印象を整える
- セキュリティや表示速度を改善する
最初に押さえてほしいポイント
リニューアルは目的が最も重要です。見た目だけの刷新に終わらないよう、数値で課題を把握し、社内で共通認識を作って進めてください。次章から具体的に説明していきます。
サイトリニューアルとは?
はじめに
サイトリニューアルとは、既存のWebサイトを目的に合わせて作り直すことです。見た目だけでなく、構造やコンテンツ、機能まで見直し、より使いやすく成果が出るサイトを目指します。
何をするのか
主に次の点を見直します。
– デザイン・レイアウトの刷新(例:配色や写真を変えて印象を統一)
– スマホ対応や表示速度の改善(例:画像の最適化、レスポンシブ化)
– サイト構造の整理(例:カテゴリを統合して探しやすくする)
– コンテンツの見直しと追加(例:商品説明や導入事例の充実)
– 機能改善(例:問い合わせフォームの簡略化、会員機能の導入)
主な目的
- ユーザー体験(UI/UX)の向上
- 検索順位や流入の改善(内部構造とコンテンツの最適化)
- 成約率(CVR)の向上(導線を改善して申し込みや購入につなげる)
- ブランドイメージの統一
- 管理しやすい運用体制の構築(CMS導入など)
実際の例
たとえば、企業サイトならトップページを見直して重要な情報を上部に置き、問い合わせボタンを常に表示します。ECサイトなら購入までのステップを短くしてカートを改善します。
注意点
目的を明確にしないままデザインだけ変えると効果が出にくいです。まず現状の課題を洗い出し、改善目標を決めて進めましょう。
サイトリニューアルの主な手順
以下は、サイトリニューアルを計画的に進めるための一般的な手順です。各工程でのポイントと具体例をやさしく説明します。
1. リニューアルの目的・課題を明確にする
何のためにリニューアルするのかを決めます。例:問い合わせ数を増やす、ブランドイメージを刷新する。目的がぶれると成果が出にくくなります。
2. 現状分析と目標設定(KGI/KPI)
アクセス状況やユーザー行動を確認し、達成したい指標を決めます。例:半年で問い合わせ数を30%増やす。
3. 要件定義とプロジェクト体制の構築
必要な機能、予算、納期を整理し、担当者や外部パートナーを決めます。連絡経路を明確にしておくと進行がスムーズです。
4. 情報設計・サイトマップ作成
コンテンツの構成を決め、ユーザーが迷わない導線を作ります。主要ページとその関係性を図にします。
5. ワイヤーフレーム・原稿作成
画面の骨格(ワイヤー)を作り、ページに載せる文章や画像を準備します。ここで要点を絞ると後工程が楽になります。
6. デザイン・UI/UX設計
ブランドに合った見た目と操作性を作ります。スマホ表示も同時に確認します。
7. コーディング・システム開発
デザインを実際のページに組み込み、必要なシステムを実装します。CMSやフォーム連携などを忘れずに。
8. テスト・動作確認
リンク切れや表示崩れ、フォーム送信の確認を行います。ユーザー視点で操作して問題がないか確かめます。
9. 公開・移行作業
旧サイトからの移行やURLのリダイレクト設定を行います。公開時のバックアップも用意します。
10. 公開後の効果測定・改善運用
アクセスやコンバージョンを定期的に確認し、改善を繰り返します。小さな改善を継続すると成果が出やすくなります。
サイトリニューアルで気をつけたいポイント
1. SEOへの配慮
サイトの構造やURLを変えると検索順位に影響します。主な対策はリダイレクトの設定とサイトマップの更新です。例えば、旧URL「/products/item1」を新URL「/shop/item1」に移す場合は301リダイレクトを設定して検索エンジンに正しい住所を伝えます。不要なコンテンツは削除前に統合やリライトを検討してください。
2. リダイレクトとサイトマップ
すべての変更先に正しいリダイレクトを貼ることが重要です。テスト用の一覧を作り、確認後に本番へ反映します。サイトマップ(XML)は最新化し、検索エンジンへ再送信してください。robots.txtも合わせて確認します。
3. バックアップとテスト環境
作業前に完全なバックアップを取り、ステージング環境で動作確認を行います。フォーム送信、画像表示、モバイル表示、読み込み速度などを実際にチェックして問題を潰します。
4. 内部リンクと導線の見直し
ページ移動や名称変更後は内部リンクが切れやすくなります。ナビゲーションやパンくずを整え、重要なページへ自然に誘導する内部リンクを強化してください。リンク切れチェックツールの利用を推奨します。
5. 運用体制と更新性の確保
サイト公開後の更新を考え、担当者と更新フローを決めます。CMSの権限やテンプレートの整備、簡単なマニュアルを用意すると運用が安定します。
6. 関係者間のコミュニケーション
デザイン、開発、マーケティングなど関係者と事前に目的やスケジュールを共有します。ローンチ直前と直後の連絡窓口を決め、問題発生時に迅速に対応できる体制を整えてください。
サイトリニューアルのタイミングと制作期間
タイミングの目安
一般的に企業は3〜6年ごとにリニューアルを検討します。デザインや技術の陳腐化、事業方針の変更、集客の低下がきっかけです。
リニューアルを検討すべきサイン
- スマホ表示が崩れる
- 問い合わせや購買が減った
- CMSやプラグインのサポートが終了
- デザインが古くブランドに合わない
制作期間の目安
- シンプルなコーポレートサイト:2〜3ヶ月
- コンテンツや機能が中規模:3〜6ヶ月
- 大規模サイトやECサイト:6ヶ月以上
期間に影響する主な要素
- 要件定義の深さ(機能や対象ページ数)
- コンテンツ準備(文章・画像・動画の有無)
- デザイン作業と承認回数
- 開発・テスト・公開作業
- 外注先や社内レビューの速度
期間を短縮する方法
- 必要最小限の機能に絞る(段階的リリース)
- テンプレートや既存部品を活用する
- コンテンツは並行して準備する
- 承認フローを簡素化する
簡単なスケジュール例(中規模)
- 企画・要件定義:3〜4週間
- デザイン:4〜6週間
- 開発:6〜8週間
- テスト・公開準備:2〜4週間
計画のコツ
余裕を持ったスケジュールを立て、重要なマイルストーンで関係者の合意を得てください。段階的に公開するとリスクを減らせます。
サイトリニューアルでよくある失敗例と対策
はじめに
サイトリニューアルでは見た目の改善に目が行きがちですが、運用やSEO、社内調整で失敗すると効果が出ません。ここでは代表的な失敗と、具体的な対策をわかりやすく説明します。
失敗例1:SEO順位の大幅下落
原因例:リダイレクトミス、URL構造の大幅変更、metaの消失
対策:
– 既存URLの一覧(CSV)を作成してリダイレクトマップを用意する。301リダイレクトを正確に設定します。
– サイトマップを更新し、Search ConsoleやBingに再送信する。
– 主要ページのtitle・meta descriptionを引き継ぐか改善版を用意し、検索意図を保ちます。
失敗例2:コンテンツの目的喪失
原因例:目的・ペルソナが不明確で内容がばらばらになる
対策:
– リニューアル前に目的(問い合わせ増、資料DLなど)を明確化します。
– ペルソナを作成し、各ページの役割を決めるコンテンツマトリクスを作成します。
– 既存コンテンツはスコアリングして残す・統合する基準を決めます。
失敗例3:デザイン重視でユーザー視点欠如
原因例:見た目だけ整えて導線が悪い
対策:
– ワイヤーフレームで導線を設計し、ユーザーテストで確認します。
– 重要な行動(CTA)を優先配置し、スマホでの操作性を重視します。
失敗例4:社内調整・進行トラブル
原因例:役割不明確、情報共有不足
対策:
– プロジェクト体制を明確にし、責任者と承認フローを定めます。
– 進捗は週次で共有し、ドキュメントを一元管理します。
– ステージング環境での確認・承認を必須にします。
発生時の緊急対策と運用チェック
- ロールバック手順を用意しておく。問題発生時は速やかに旧サイトに戻せるようにします。
- ローンチ後はGAなどでトラフィック、CTR、エラーを24〜72時間は集中監視します。
各対策は小さなチェックリストにして運用に落とし込みます。事前準備と確認を丁寧に行えば、リニューアルは失敗を避けて成果につながります。
サイトリニューアル成功のためのポイント
1 事前準備を徹底する
目的、対象ユーザー、KPI(例:問い合わせ数、CVR)を明確にします。現状サイトのアクセス解析や競合調査を行い、改善点を具体化してください。要件定義書を作り、関係者で合意を得ると後のズレを防げます。
2 SEOと導線設計を同時に考える
検索流入や既存ユーザーの導線を意識して情報設計します。例えば、主要ページへ1クリックで到達できるナビや、問い合わせボタンを目立たせる配置を検討してください。
3 運用体制と役割分担を決める
公開後の更新や保守は事前に担当を決めておきます。CMSの権限設定やマニュアルを用意すると運用が安定します。
4 制作会社との連携を密にする
定期ミーティングで進捗と要件のすり合わせを行ってください。デザイン・技術・コンテンツの責任者を明確にすると意思決定が速くなります。
5 テストと公開準備を怠らない
ブラウザやスマホで表示確認、フォーム送信テスト、解析タグの動作確認を行います。公開直前のチェックリストを用意すると漏れを防げます。
6 公開後はPDCAで継続改善する
アクセスや行動データをもとに仮説を立て、改善を繰り返します。A/Bテストやユーザーヒアリングを取り入れると効果が分かりやすくなります。