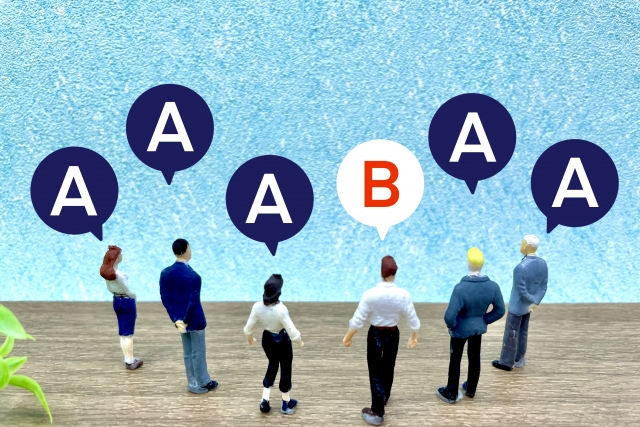はじめに
目的
本記事は、AWS Direct Connectというサービスの全体像と具体的な接続方法、構築手順をやさしく解説することを目的としています。専門用語は最小限にし、具体例を交えて分かりやすく説明します。
本記事で扱う内容
- Direct Connectの特徴(専用線でAWSと接続し、安定した通信と高いセキュリティを得る仕組み)
- 接続方式の種類と選び方
- 実際の構築手順の流れ
- 利用時のポイントや注意点、他の接続方法との比較
- 構築事例と運用のコツ
想定読者
クラウド接続の基本を知りたいIT担当者や、オンプレミス環境とAWSをもっと安定してつなぎたい方を想定しています。ネットワークの専門家でなくても理解できるよう配慮しています。
読み方の案内
章ごとに段階を追って解説します。まず第2章でサービスの全体像を掴み、第3章以降で選び方や構築手順、運用のポイントを学べます。具体例を多く示しますので、実際の導入検討にも役立ててください。
AWS Direct Connectとは
概要
AWS Direct Connect(ダイレクトコネクト)は、企業のデータセンターやオフィスをインターネット経由ではなく専用回線でAWSへつなぐサービスです。光ファイバーを使い、オンプレ側のルーターからDirect Connectロケーションまで物理的に接続します。これにより通信経路がインターネットと分離され、安定性やセキュリティが向上します。
仕組み(かんたん説明)
実際はルーターとAWS側の設備をイーサネットで接続し、VLAN(仮想回線)ごとに仮想インターフェース(VIF)を作ります。例えば、VPCへつなぐ「プライベートVIF」と、S3などのパブリックサービスへつなぐ「パブリックVIF」があります。パートナー業者を通す「ホステッド接続」も利用できます。
主なメリット
- 安定した帯域と低遅延:大量データ送受信に適します。
- 高いセキュリティ:トラフィックがインターネットを通りません。
- コスト面の利点:データ転送量が多い場合、長期的に割安になることがあります。
利用シーン(具体例)
- 大容量バックアップやログ転送
- オンプレとクラウドのハイブリッド運用(データベース複製など)
- 支店や拠点からクラウドへ安定的に接続する場合
注意点(簡潔に)
物理接続が必要なため準備期間や費用がかかります。ロケーションが近いか、キャリアやパートナーの選定、BGPなどのルーター設定が必要です。可用性確保のために冗長化を検討してください。
Direct Connectの接続方式の種類
概要
AWS Direct Connectの接続方式は大きく2つに分かれます。専用接続(Dedicated Connection)とホスト型接続(Hosted Connection)です。用途や規模に応じて選べます。
専用接続(Dedicated Connection)
物理的に1社専用のイーサネット回線を用意する方式です。帯域は高く、一般的に1Gbpsや10Gbpsなどを選べます。大容量のシステムや本番環境に向きます。利点は安定した性能とセキュリティの高さです。欠点は初期費用や手続きが比較的重く、導入までに時間がかかることです。
例:オンプレの基幹系サーバーとVPCを安定接続して大量データを転送する場合に適します。
ホスト型接続(Hosted Connection)
AWSパートナー(通信事業者やプロバイダー)が既に持つ物理回線を借りて利用する方式です。小規模や検証環境、短期プロジェクトに向きます。プロバイダーが回線を分割して提供するため、比較的短期間で利用開始できます。利点は導入が速く費用を抑えやすい点です。欠点は専用接続ほどの帯域確保や柔軟性がない場合がある点です。
例:開発チームがテストで数百Mbpsの接続を短期間確保したい時に便利です。
選び方のポイント
- トラフィック量が多く継続的なら専用接続を検討してください。安定性とセキュリティが優先されます。
- 短期利用や導入コストを抑えたい場合はホスト型が向きます。
- 冗長化が必要なら複数回線やLAG(回線結合)を検討してください。
補足:どちらもVPCへは仮想インターフェース(プライベート/パブリック)を作って接続します。用途に合わせて使い分けてください。
接続までの流れ(構築手順)
前提
Direct Connect を始める前に、AWSアカウント、接続先のロケーション、オンプレ側のネットワーク情報(ASN、IPレンジ)を用意します。回線の種別(専用接続/ホスト型)で手順が少し変わります。
1. 接続の申し込み
- 専用接続:AWSコンソールからDirect Connectを申し込みます。回線帯域やロケーションを選びます。
- ホスト型:認定パートナー経由で申し込みます。パートナーが物理接続を手配します。
2. 物理接続の確立
Direct Connectロケーションで、顧客ルーターとAWS側設備をイーサネットで接続します。ケーブルやSFPの型番、VLANタグの指定が届くので、それに従って接続します。
3. 仮想インターフェイス(VIF)の作成
AWSコンソールでVIFを作成します。用途に応じてプライベートVIF(VPC接続)かパブリックVIF(AWSパブリックサービス)を選びます。VLAN IDやBGPのASN、ピアIPを入力します(例:VLAN 101、オンプレASN 65000)。
4. オンプレ側ルーターの設定
サブインターフェイスに該当VLANを設定し、BGPでAWSとピアリングします。例:サブインターフェイスにIPを割り当て、neighborにAWSのピアIPを設定してBGPセッションを確立します。
5. 動作確認と運用開始
- BGPがEstablishedになることを確認します(例:show ip bgp summary)。
- ルートが受信できているか、VPCのエンドポイントへpingで疎通確認します。
- 問題があればログやコンソールのステータスを確認し、パートナーやAWSサポートに連絡します。
ポイント:作業は営業時間外やメンテ時間に実施すると影響を抑えやすいです。また、冗長化構成(複数接続)も検討してください。
Direct Connect利用時のポイントと注意事項
回線速度と選択
専用接続は通常1Gbps以上の帯域を確保できます。ホスト型(AWSパートナー経由)は50Mbps単位で選べることが多く、小容量から段階的に増やせます。用途に合わせて余裕を持った帯域を選んでください。例えばデータ転送が多い場合は余裕を見て2倍程度の容量を想定すると安心です。
冗長化と設計の考え方
重要な通信は必ず冗長化します。最低でも2系統の回線を異なる設備経路で引き、障害時は自動で切り替わる構成を用意します。AWS側ではLAG(リンク結合)や複数の仮想インターフェースを使って冗長化できます。切替えのテストを事前に行い、運用手順を明確に残してください。
コストと費用感
初期費用と月額費用が発生し、一般にVPNより高くなります。しかし帯域保証や通信の安定性を重視する場合に適しています。費用は回線容量、設置工事、ロケーション、長期契約で変動しますので見積りで比較してください。
設定と運用の注意点
物理配線、VLAN設定、BGP(経路交換)の基礎知識が必要です。BGPは経路を自動で渡す仕組みですが、プレフィックスのフィルタリングやAS番号設定など注意点があります。MTUやルーティングポリシーの整合性も確認してください。
セキュリティと暗号化
Direct Connect自体はトラフィックを専用線で分離しますが、暗号化は標準ではありません。機密性が必要なら、アプリケーション層での暗号化や別途VPN併用を検討してください。
運用の実務チェックリスト
- 回線キャパシティと予備を見積もる
- 冗長経路の物理的分離を確認
- BGPのタイマー、フィルタを設定してテスト
- 監視(アラーム)とログを準備
- メンテ時間とベンダ連絡先を明確化
- 切替え・障害対応手順をドキュメント化
以上を押さえると、安定した接続と運用がしやすくなります。必要なら具体的な設計や設定例もご案内します。
他のAWS接続方法との比較
比較対象と前提
この章では主にDirect ConnectとSite-to-Site VPN(IPsec)、インターネット経由(HTTPSなど)、およびTransit Gatewayを比較します。用途別に分かりやすく説明します。
安定性と帯域品質
Direct Connectは専用回線を使うため遅延や揺らぎが少なく、大容量データやリアルタイム処理に向きます。Site-to-Site VPNは公衆網を使うため帯域変動が起きやすく、短時間の利用や低帯域用途に適します。インターネット経由はさらに変動しやすいです。
セキュリティ
どちらも暗号化やファイアウォールと組み合わせれば安全に使えます。Direct Connectは物理的に分離された経路を持つため機密性の高い通信に向きます。VPNは暗号化で保護しますが、経路は公衆網に依存します。
コストと導入の容易さ
初期費用と月額が高めなのがDirect Connectです。一方、VPNは低コストで短期間に導入しやすいです。Transit Gatewayは複数VPCや拠点を集約する際に便利ですが、利用量で費用が増えます。
運用性と拡張性
拠点やVPCが多い場合はTransit Gatewayと組み合わせると運用が楽になります。帯域増強が必要ならDirect Connectで専用容量を確保し、拠点間はVPNで補うと柔軟です。
選び方の目安
- 高信頼・大容量データ転送:Direct Connectを検討してください
- 低コスト・短期導入:Site-to-Site VPNやインターネット経由が向きます
- 多拠点をまとめて管理:Transit Gatewayを組み合わせると効果的です
構築事例・運用のコツ
代表的な構築パターン
- 冗長化構成:複数ロケーション(例:拠点Aと拠点B)と複数キャリア(キャリアA/キャリアB)で回線を用意します。どちらか切れてももう一方で通信を維持できます。
ネットワーク分離とルーティング
- VPCやサービスごとに専用の仮想インターフェース(VIF)を使い、アクセス権を分離します。経路制御はBGPのルートフィルタやコミュニティで行います。例えば、相手側には必要最小限のプレフィックスだけを通知します。
ルーター設定のポイント
- BGPでのプレフィックス制御、ASパスプリペンド、メトリック調整を活用します。ルートフィルタで不要な経路を拒否し、ループ防止のために適切なタイマーを設定します。機器ベンダーのベストプラクティスに従ってください。
パートナー選定と契約
- Direct Connectの実績がある認定パートナーを選び、設置・保守・オンサイト対応の範囲とSLAを明確にします。接続要件(帯域、冗長度、導通保証)を見積書に反映してください。
運用と監視
- 接続状態やBGPのピア状況を常時監視し、アラートを設定します。定期的にフェイルオーバーテストを行い、変更時は事前に影響範囲を確認してロールバック手順を用意します。
テストと定期見直し
- 回線故障や経路変化のシミュレーションを行い、設定や手順を検証します。トラフィック増加に備えて帯域や設計の見直しを定期的に行ってください。