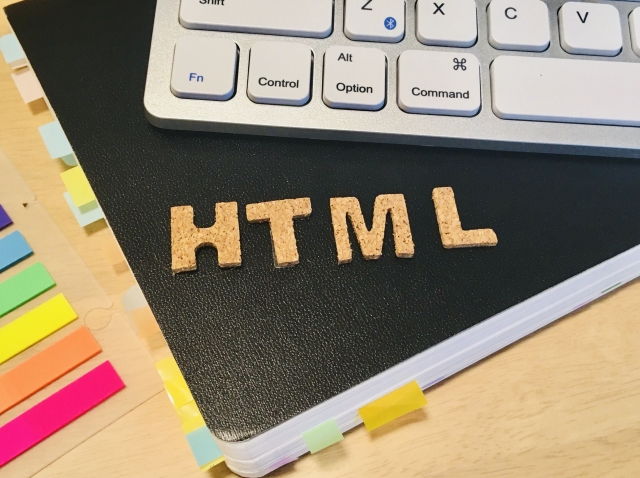はじめに
本章の目的
本章では、本記事全体の目的と読み進め方をやさしく説明します。本記事は学術データベース「Web of Science」を初めて使う方や、使い方を見直したい研究者・学生を主な対象としています。
対象読者
- 研究論文の文献検索を行う学生や研究者
- 引用やインパクトを確認したい研究支援担当者
- データベースの違いを比較したい図書館職員
この記事で得られること
- Web of Scienceの基本的な役割と収録範囲の理解
- 引用データや文献間の関係をどう利用するかの概要
- 実際の検索や分析の始め方、便利な機能の紹介
- 他の主要データベースとの比較ポイント
読み方のヒント
各章は独立して読めるように構成しています。まず第2章で概要をつかみ、実際に使いたい場合は第4章の手順を参照してください。用語が出てきた際は具体例を示すので、専門用語に詳しくなくても理解しやすく書いています。
Web of Scienceの概要と機能
概要
Web of Scienceは1900年から現在までの厳選された学術雑誌を収録する有料の文献データベースです。大学や研究機関が契約して利用します。論文の検索だけでなく、引用関係を基にした分析や研究者の情報管理を支援します。
主な機能
- 論文検索:キーワード、著者名、雑誌名などで絞り込めます。具体例として「再生医療」に関するレビューだけを探すことが可能です。
- 引用分析:被引用数や引用ネットワークを確認できます。ある論文を起点に、どの研究がそれを引用したか追えます。
- 被引用参照検索:論文の参考文献リストから関連研究をたどれます。
- 研究者プロフィール:著者ごとの業績一覧や識別子(例:ORCID)と連携します。
- アラートと保存:新着論文の通知や検索条件の保存、文献リストのエクスポートができます。
- 他ツールとの連携:文献管理ソフト(例:EndNote)と連携し、書誌情報を取り込めます。
利用例
- 新しい研究分野の総説を素早く見つける。
- 自分や他者の論文の影響力を数値で把握する。
- 共同研究候補者の研究履歴や引用関係を確認する。
利用上の注意
機関契約が必要で、全文が常に含まれるわけではありません。必要な場合は図書館や所属機関を通じて全文入手してください。
Web of Scienceの特徴
厳選された学術誌の収録
Web of Scienceは査読済みで質の高い学術誌を中心に収録しています。たとえば医学や工学の主要ジャーナルを網羅するため、信頼性の高い論文を探したいときに便利です。Google Scholarより収録基準が厳しいため、ノイズの少ない検索結果が得られます。
引用データの正確性
引用数を丁寧に集計し、どの論文がどの論文を参照しているかが明確に分かります。引用数を指標にして研究の影響力を把握できます。具体例として、ある論文が複数分野で引用されていれば、研究の波及効果が見えやすくなります。
文献間の関係性の分析
先行文献(Cited)と後続文献(Citing)を簡単にたどれます。引用ネットワークを辿ることで、研究の流れや重要な論点を素早く把握できます。たとえば、あるテーマの代表的な論文から関連研究を幅広く抽出し、研究背景の整理に役立てられます。
活用のヒント
・重要論文を見つけたら「引用元」と「被引用」を両方確認すると関連研究を効率的に集められます。
・キーワード検索後に被引用数で並べ替えると、影響力の高い論文を優先して閲覧できます。
Web of Scienceの利用方法
検索の基本
- キーワード入力で始めます。例:「遺伝子 発現」「気候変動 経済」など、主要語を入れて検索します。
- 検索窓には著者名、誌名、DOIなども入れられます。具体例:著者に「Tanaka T」と入れるとその著者の論文を絞れます。
絞り込みと並べ替え
- 結果は年、分野、文献種別(論文、総説など)で絞れます。最近の研究だけを見たい時は年で絞ってください。
- 並べ替えは「関連度」「被引用数」「発行日」などを選べます。被引用数で並べ替えると影響力の大きな論文を上位にできます。
被引用数を使った探索
- 被引用数はその論文がどれだけ参照されたかを示す目安です。多く引用されている論文は分野で重要な位置にあることが多いです。
- 具体的には、検索結果で被引用数の高い順に並べ、レビューや基礎研究を確認します。
関連文献の見つけ方
- 特定の論文を開くと「引用文献(References)」と「被引用文献(Times Cited)」が表示されます。引用文献から先行研究を、被引用文献からその論文を参照した後続研究を見つけられます。
- 類似文献を自動で提案する機能も使えます。テーマに沿った別論文を効率的に収集できます。
保存・エクスポートと通知機能
- 気になる論文はマイリストに保存できます。複数選んで一括でエクスポート(BibTeXやRIS)できるため、文献管理ソフトに取り込みやすいです。
- 検索条件を保存して新着通知を受け取れます。定期的に最新研究を把握するのに便利です。
Web of Scienceと他のデータベースとの比較
比較のポイント
利用目的に応じて使い分けます。検索の網羅性、引用数の正確さ、使いやすさ、費用が主な比較点です。具体例を交えて説明します。
Google Scholarとの比較
Google Scholarは無料で幅広く論文・学位論文・プレプリント・学会資料などを拾います。たとえば会議資料や大学のリポジトリにある論文も見つかります。ただし引用数に重複が混ざることがあり、精度は落ちる場合があります。一方、Web of Scienceは収録基準を設けたジャーナル中心で、引用データの整合性を重視します。引用数の比較をすると、GSの数が多く出ることがありますが、Web of Scienceの数はより検証しやすいです。
Scopusとの比較
Scopusは収録範囲が広く、特に欧米やアジアの学術誌を多く含みます。収録基準やインデックスの方法がWeb of Scienceと異なるため、同じ論文でもカバレッジや引用数に差が出ます。研究評価や文献レビューでは、両方を照合すると不足が減ります。
その他のデータベース
PubMedは医学・生命科学に強く無料で使えます。分野特化のデータベース(例:IEEE Xplore)は工学分野で有用です。
選び方の目安
- 費用を抑え幅広く探したい:Google Scholar
- 引用分析や正確なメタデータが必要:Web of Science
- 広いジャーナルカバレッジを重視:Scopus
複数を組み合わせると、より信頼できる検索と評価が可能です。