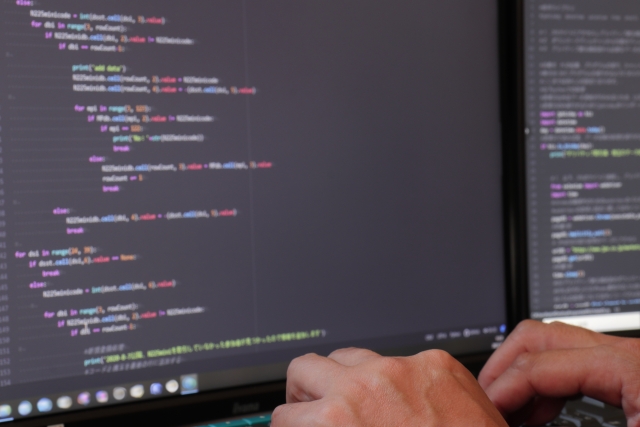はじめに
本書の目的
本書は、AWSが提供するデータベース移行支援サービス「AWS Database Migration Service(AWS DMS)」の全体像を分かりやすく紹介することを目的としています。移行の基本や利点、構成要素、実際の利用フロー、運用上の注意点まで順を追って解説します。
読者想定
- オンプレミスや他クラウドのデータベースをクラウドに移したい方
- 移行でダウンタイムを抑えたいシステム担当者や開発者
- 移行の計画や運用方針を理解したいマネージャー
具体例として、社内のMySQLをAmazon RDSへ移行するケースを念頭に置いて解説します。
本章で得られること
この「はじめに」では、読者が本書の目的と構成をつかみ、どの章で何を学べるかを明確にします。続く章で実務に役立つ知識を丁寧に説明します。
AWS DMSの概要
何をするサービスか
AWS Database Migration Service(AWS DMS)は、データベースの中身を別の場所へ安全に移すためのサービスです。オンプレミスや他クラウド、AWS内のデータベースから別のデータベースへデータをコピーしたり、継続的に同期したりできます。たとえば、社内のMySQLからAWSのRDS MySQLへ、あるいはOracleからPostgreSQLへ移行する場面に向きます。
対応するデータベース例
- RDBMS:MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server など
- NoSQL:MongoDB など
- データウェアハウス:Amazon Redshift など
これらの間で同種・異種を問わず移行できます。
主な移行方式
- フルロード:既存データを一括でコピーします。移行開始時に実行します。
- 継続的レプリケーション(CDC):変更分だけを追いかけて反映します。稼働中のシステムでもダウンタイムを小さくできます。
使われる場面の例
- オンプレミスからクラウドへ移すとき
- データベースのバージョンやエンジンを変えるとき(例:Oracle→PostgreSQL)
- 本番と分析基盤を分離してデータを複製するとき
補足
設定やネットワーク準備、互換性の確認は必要です。次章で特徴や利点、具体的な仕組みを丁寧に説明します。
主な特徴とメリット
概要
AWS DMS(Database Migration Service)の主な特徴と、それがもたらすメリットを分かりやすく説明します。具体例を交えながら、どのような場面で役立つかを示します。
異種DB間移行対応
異なる種類のデータベース間でもデータ移行できます。例:オンプレミスのOracleからAWSのAurora PostgreSQLへ移す場合でも、スキーマやデータ型の違いを考慮しながら移行できます。DBの種類が違っても対応できる点が大きな利点です。
ダウンタイム最小化(CDC)
稼働中のデータベースを止めずに移行できます。初回は全データを移し、その後は変更分(CDC:変更データキャプチャ)をリアルタイムで同期するため、サービス停止を最小限に抑えられます。
自動化と簡易化
ウィザード形式の管理画面で設定が分かりやすく、専門知識がなくても基本的な移行作業を行えます。テンプレートや監視機能により作業工数を削減できます。
多様な移行シナリオ
オンプレミスからクラウド、クラウド間、AWSリージョン間など、さまざまなパターンに対応します。段階的な移行やレプリケーション用途にも使いやすいです。
コスト効率
従量課金制のため、使った分だけ費用が発生します。短期間や段階的な移行では固定費を抑えられ、コスト管理がしやすくなります。
構成要素と仕組み
AWS DMSは主に3つの要素で構成され、これらが連携してデータ移行を実行します。以下で役割と仕組みをやさしく説明します。
エンドポイント
移行元と移行先の接続情報を定義します。たとえば、オンプレのMySQLを指定する移行元エンドポイントと、RDSのAuroraを指定する移行先エンドポイントを用意します。接続先のホスト名、ポート、ユーザー名、パスワードを設定し、必要に応じて接続テストを実行します。
レプリケーションインスタンス
実際にデータを移す処理を行うEC2ベースのインスタンスです。軽負荷向けのT系、処理重視のC系、メモリ重視のR系、もしくはサーバーレスを選べます。高可用性が必要ならマルチAZ構成にして、障害時のフェイルオーバーを可能にします。
データ移行タスク
移行の種類と対象を定義します。主なタイプは「フルロード(初回全件移行)」「CDC(変更データの継続適用)」「フルロード+CDC(初回移行後に差分同期)」です。テーブル単位で移行対象やフィルタ条件、列の変換ルールを指定できます。
データの流れ(仕組みの概略)
1) レプリケーションインスタンスが移行元のログやテーブルを読み取る
2) 読み取ったデータを必要に応じて変換・マッピングする
3) 移行先へ書き込む
CDCでは移行元のトランザクションログを監視し、発生した変更だけを順次適用します。
運用面の注意点
ネットワーク接続やDB権限、移行対象のサイズによって性能が変わります。事前にパフォーマンステストを行い、レプリケーションインスタンスの種類や容量を調整してください。
基本的な利用フロー
概要
AWS DMSでの移行は、準備→実行→検証の順で進めます。ここでは実務で使う具体的な手順と注意点をやさしく説明します。
1. ソース/ターゲットDBの設定
コンソールで移行元(例:オンプレMySQL)と移行先(例:Amazon Aurora)の接続情報を登録します。ユーザー権限やネットワーク(VPC、サブネット、セキュリティグループ)も確認してください。簡単なテスト接続を必ず行います。
2. レプリケーションインスタンス作成
移行処理を実行するインスタンスを作ります。データ量や同時タスク数に応じてスペックを選びます。小規模ならt3系、大量移行ならメモリ/CPUを増やします。
3. 移行タスク作成
「フルロード」「CDC(継続的変更)」など方式を選び、対象テーブルやカラムを指定します。最初は小さなテーブルで試し、設定を調整すると安全です。
4. 移行実行とモニタリング
移行を開始したらコンソールやCloudWatchで進捗を確認します。ログやエラーを随時チェックし、必要ならリトライや調整を行います。ネットワークやI/Oがボトルネックになりやすい点に注意します。
5. 移行完了・検証
ターゲットDBのレコード数やサンプル照合、アプリケーションの動作確認を行います。ダウンタイムを最小化する場合は、最終差分を適用してから切り替える運用を取ります。切り替え後は監視を強化してください。
セキュリティ・運用のポイント
SSL/TLSによる暗号化
エンドポイント間の通信はSSL/TLSで暗号化できます。設定をしないと警告が出るため、必ず有効化を検討してください。具体例としては、ソース・ターゲット両方のエンドポイントで「SSLを有効」にし、必要に応じてCA証明書を検証します。保存データはKMSで暗号化することを合わせて推奨します。
パブリックアクセス制御
レプリケーションインスタンスをインターネット公開しない設定にすることが基本です。セキュリティグループでアクセス元を限定し、0.0.0.0/0や広域の許可を避けます。例として、データベースがあるVPC内のサブネットとアプリケーションサーバーのIPレンジだけを許可します。
運用監視
CloudWatchとDMSの監視機能で移行状況やパフォーマンスを常時確認します。重要指標はCPU使用率、ディスク空き容量、レプリケーション遅延(レイテンシ)、エラー数などです。しきい値を決めてアラームを設定し、遅延やエラー発生時に通知を受け取る運用を組みます。
ログ管理と障害対応
DMSタスクのログやエラーログをCloudWatch LogsやS3に保存し、長期保管と検索をしやすくします。障害発生時はログを基に原因切り分けを行い、必要ならばタスクの再起動や該当テーブルのフルロード再実行を行います。定期的に復旧手順(Runbook)を整備してください。
アクセス権と鍵管理
DMSがS3やKMSへアクセスするためのIAMロールは最小権限で構成します。認証情報はローテーションし、KMSで鍵管理を行うことでキー漏洩リスクを下げます。運用チームの権限分離とログ監査も実施してください。
よくある利用シーン・事例
1. オンプレミスからAWSへのクラウドリフト
オンプレミスのデータベースをクラウドに移して運用コストを下げ、可用性を上げたい場合に使います。AWS DMSは稼働中のデータを段階的に移せるため、業務停止を最小限に抑えられます。例:社内のOracle DBをAmazon RDSに移行し、切替を夜間に実施する。
2. クラウド間のDB移行
他社クラウドやAWS内の別サービスへ移行する際に利用します。データ転送を自動化でき、移行中の同期も維持します。例:GCPのCloud SQLからAWSのRDSへデータを移す。
3. リアルタイム分析基盤との連携(CDC)
更新が発生した差分だけを送り、分析基盤にほぼリアルタイムでデータを反映できます。RDSからRedshiftやSnowflakeへ連携し、最新の分析結果を保てます。短い遅延で履歴を追いたい分析に向いています。
4. 異種DB間の移行(例:SQL Server → Aurora PostgreSQL)
データ型やSQL方言が異なる場合でも、DMSとスキーマ変換ツールを組み合わせれば移行を進められます。例として、SQL ServerからAurora PostgreSQL(Babelfishを活用)へ段階的に移す際に有効です。移行前に型差の確認とテストを十分に行ってください。
どのケースでも事前の検証、ネットワーク帯域やデータ整合性の確認、移行後の監視が重要です。
注意点・制約
DBエンジンやバージョンによるサポート差
AWS DMSは多くのエンジンを扱えますが、同じ機能やデータ型が全てのバージョンで動くとは限りません。事前に移行元・移行先の互換性を確認し、サポート外の型や拡張機能がないか洗い出してください。サンプルデータで検証すると問題点が見つかりやすいです。
アプリケーション側の対応は別途必要
DMSはデータの複製・同期を行いますが、アプリケーション固有のロジックやDBパラメータ調整は対象外です。接続文字列、SQLの方言、トリガーやストアドプロシージャの動作確認を行い、必要ならアプリ側修正や運用手順の変更を準備してください。
移行計画とリハーサルの重要性
大規模や商用システムでは一度の移行で完了させず、複数回のテスト移行とリハーサルを行ってください。性能確認、ダウンタイム最小化、ロールバック手順の検証を必ず実施します。実稼働データに近い負荷での検証が特に有効です。
その他のよくある制約
- 大きなLOBやバイナリは転送に時間がかかる。分割や別同期方式を検討してください。
- トランザクション整合性や時差の扱いに注意。CDC(変更データキャプチャ)では遅延が発生することがあります。
- ネットワーク、権限、暗号化設定の確認を忘れずに。
以上を踏まえ、事前調査・テスト・運用手順の整備を優先して進めてください。
まとめ
AWS DMSは、データベースを安全かつ効率的に移行・統合するための有力な選択肢です。最低限のダウンタイムでデータを移動でき、オンプレミスからクラウド(例:RDS)への移行や、MySQLからPostgreSQLへのような異種DB間のデータ連携にも対応します。運用面はマネージド型で負荷を軽減できます。
主なポイント
- ダウンタイムを抑えた移行が可能:継続レプリケーションで本番停止を短くできます。
- 異なるDB間でも対応:データ型の違いに注意すれば移行できます。
- 運用負荷の軽減:設定や監視をクラウド側で補助します。
導入時の実務的な手順(簡易チェックリスト)
- 目的と対象テーブルを明確にする
- 小規模なパイロットで手順を検証する
- スキーマ差分やデータ型の変換を確認する
- 移行前に必ずバックアップを取得する
- レプリケーション遅延やエラーを監視する設定を行う
- 切り戻し手順を用意する
総括
AWS DMSはクラウド移行やデータ統合の基盤作りに向くサービスです。まずは小さなケースから試し、運用ルールと監視を整えてから本番移行を行うことをおすすめします。