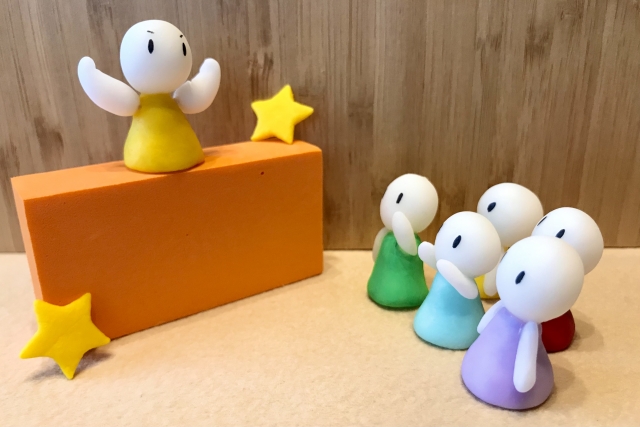はじめに
背景
本ドキュメントは、検索キーワード「web制作 流れ ワイヤーフレーム」を念頭に置き、Web制作の全体像とワイヤーフレームの役割をわかりやすく整理したものです。これから制作に携わる方や、発注側の方にも役立つ内容を目指します。
本書の目的
・Web制作の各工程を順序立てて理解してもらうこと
・ワイヤーフレームがいつ・なぜ必要かを具体的に示すこと
・実務で使える手順や注意点、ツールの紹介につなげること
対象読者
・初めてWeb制作に関わる方
・ワイヤーフレームの活用を学びたいディレクターやデザイナー
・外注や社内調整をスムーズにしたい発注者
この記事の読み方
章ごとに流れ、役割、作り方、注意点、道具を順に解説します。まずは全体像をつかみ、必要な章を重点的に読んでください。具体例を交えて丁寧に説明しますので、気軽に読み進めてください。
Web制作の全体フローとワイヤーフレームの位置付け
全体フローの概要
Web制作は一般に次の工程で進みます。
1. ヒアリング・要件定義:目的、ターゲット、機能を決めます。
2. サイト構成(サイトマップ):ページ構成と導線を整理します。
3. ワイヤーフレーム作成:各ページのレイアウトや情報配置を視覚化します。
4. デザイン制作:色・画像・タイポグラフィを決定します。
5. コーディング・開発:実装して動作させます。
6. テスト・修正:動作確認と調整を行います。
7. 公開・運用開始:公開してアクセスを集めます。
8. 運用・改善:データを見て改善します。
ワイヤーフレームの位置付けと役割
ワイヤーフレームは要件定義とデザインの間に位置します。ページの情報優先順位と導線を決める設計図です。例えばトップページで目立たせるCTA(行動喚起ボタン)の位置や、ユーザーが情報を見つけやすい順番を確かめます。クライアントや開発チームの認識を揃える役割も果たします。
誰が関わり、どんな成果物が出るか
関わるのはディレクター、UXデザイナー、クライアント、エンジニアです。成果物はページごとのワイヤーフレーム(PDFやツールのファイル)、主要な導線図、注記(機能や優先度)です。簡易なものは手描きでも構いません。
実務でのポイント
・主要な画面と導線を優先して作ること。
・クライアントと早めに確認して合意を取ること。
・デザインに入る前に機能や優先順位を決めること。
これらを守ると無駄な手戻りを減らせます。
ワイヤーフレームとは何か?その役割と目的
定義
ワイヤーフレームは、Webページの骨組みを示す設計図です。画像や見出し・段落・ボタン・メニューといった要素の配置だけをシンプルな図で表します。色や細かなデザインは省き、情報の構造と優先順位に注目します。
主な役割
- 情報の優先順位を決める:何を目立たせるかを明確にします。
- 要件の共有:クライアントやチームで「何を作るか」をすり合わせます。
- 問題の早期発見:動線の抜けや要素の不足をデザイン前に見つけられます。
具体例
トップページなら、主要な製品画像と購入ボタンを上部に配置し、詳しい説明は下へ置くなど、ユーザーの行動を想定して配置を決めます。問い合わせページでは、入力項目の順番や必須項目をはっきりさせます。
忠実度(Fidelity)の違い
- 低忠実度:手書きや簡単な線と枠。アイデア出し向け。
- 中忠実度:線画で細かなレイアウト指定。要件確認向け。
- 高忠実度:ほぼ完成図。デザインやコーディングへの橋渡しに使います。
誰が・いつ使うか
デザイナー、ディレクター、開発者、クライアントが使います。要件定義後、ビジュアル作業の前に作成すると効果的です。
ワイヤーフレームを作る価値
作業のムダを減らし、認識のズレを防ぎます。早めに共有することで、後工程の手戻りを少なくできます。
Web制作におけるワイヤーフレーム作成の流れ
はじめに
ワイヤーフレーム作成は、情報をかたちにして関係者と共有する作業です。ここでは実務で使える順序と具体的なポイントを分かりやすく説明します。
1. 情報設計・要素のリストアップ
まずサイトの目的、想定ユーザー、必須機能を洗い出します。例えば「問い合わせを増やす」なら、問い合わせ導線やフォーム項目を最優先でリスト化します。成果物は要件リストやコンテンツ一覧です。
2. 情報の整理と優先順位付け
ユーザー視点で重要度を決め、ページごとの掲載量を決めます。トップに何を置くか、サイドバーは必要かを判断します。優先度は高・中・低で分けると整理しやすいです。
3. ラフスケッチ・サイトマップ作成
紙やホワイトボードでざっくりレイアウトを描き、ページ同士のつながり(サイトマップ)を作ります。ここでは細かいデザインは不要で、導線と情報配置を確認します。手書きは早くて有効です。
4. デジタル化・清書
専用ツールやPowerPointでワイヤーフレームを作成し、注釈を付けます。ボタンの動きや重要な制約はコメントで明記します。グリッドを使い余白やサイズを揃えると後のデザインがスムーズです。
5. 関係者と共有・フィードバック
チームやクライアントに見せ、意図を説明して意見を受け取ります。フィードバックは必ず記録し、優先順位を付けて修正します。必要ならユーザーテストで簡単な確認を行ってください。
実務のコツ
時間を区切って進める(例:ラフは30分)、主要ページを先に作る、変更履歴を残すと後で役立ちます。ユーザーの立場に立って何が一番分かりやすいかを常に意識してください。
ワイヤーフレーム作成時のポイントと注意点
概要
ワイヤーフレームは最終デザインの叩き台です。ここでは作成時に意識すべき重要点と注意点を、実務で役立つ具体例とともにご紹介します。
1. まずサイト全体構成を固める
ページ階層と導線を先に決めます。サイトマップを作り、主要な役割(トップ、一覧、詳細、お問い合わせなど)を明確にしてください。これにより抜けや重複を防げます。
2. 優先度の高いページから作る
訪問者が最初に触れるページやコンバージョンに直結するページを先に作成します。例えばランディングや商品詳細を先に詰めると改善効果が分かりやすくなります。
3. SEOとターゲットキーワードを意識する
見出しや導線に狙うキーワードを反映してください。コンテンツ構造が検索に影響しますので、見出しの階層や導線を設計段階で確認します。
4. 情報の抜け漏れ・過剰に注意
必要な要素(連絡先、CTA、法的表記など)をチェックリスト化します。一方で要素を詰め込み過ぎるとユーザーが迷うため、優先順位で表示を決めます。
5. 実務的な工夫
- 注釈を付けて意図を伝える(動きや優先度など)
- モバイルファーストでレイアウトを検討する
- 標準コンポーネントをテンプレ化して効率化する
- バージョン管理とレビュー履歴を残す
6. 柔軟に改善する前提で作成する
ワイヤーフレームは試作です。ユーザーテストやチームからのフィードバックを受けて繰り返し改善します。プロトタイプや簡単なユーザーテストで早めに確認してください。
おすすめツールと制作効率化のヒント
1. デジタルデザインツール(おすすめ)
Figma、Adobe XD、Sketchはワイヤーフレーム作成でよく使われます。どれも画面をパーツ化して再利用できます。Figmaはブラウザで共有しやすく、共同編集が簡単です。
2. 手軽に作るなら
PowerPointやExcelは非デザイナーでも扱いやすく、クライアント向けの簡易ワイヤーを素早く作れます。図形や表を使ってレイアウトを示し、PDFで渡せます。
3. アイデア出しは手書きで
ラフは紙やホワイトボードで速く描くと良いです。手早く何案も比べられ、初期の意見出しに向きます。
4. 制作効率化の具体的ヒント
- テンプレートを用意して毎回0から作らない
- ヘッダー・フッター・ナビなど再利用できるパーツをコンポーネント化する
- カラーパレットや文字サイズのルールを決めておく
- よく使うアイコンや画像はアセットとしてまとめる
5. コラボレーションの工夫
共有リンクやコメント機能を活用してフィードバックを集めます。バージョン管理を習慣にすると差分が追いやすくなります。
6. 小さな時短テクニック
キーボードショートカットを覚える、プラグインでダミーテキストやアイコンを自動挿入する、よく使う部品をライブラリ化するだけで作業が大幅に速くなります。
まとめ―ワイヤーフレームを活用したWeb制作のメリット
ワイヤーフレームは、Web制作における設計図の役割を果たします。制作の初期段階で関係者の認識を揃えることで、後工程での手戻りを減らし、制作全体の効率を高めます。
主なメリット
-
認識のズレを防げる:画面構成や導線を視覚化することで、クライアントと制作側の意図が一致します。例えば、ボタンの配置や優先表示する情報を事前に決めると、デザイン段階でのやり直しが少なくなります。
-
ユーザー視点で設計しやすい:ワイヤーフレームでユーザーの動線や情報の優先順位を確認できます。簡単なプロトタイプにして実際に触ってもらえば、分かりにくい部分を早めに改善できます。
-
デザインとコーディングが効率化する:レイアウトや要素の役割を決めておくと、デザイナーとコーダーが同じ設計に基づいて作業できます。結果として、作業時間とコストの削減につながります。
活用のポイント
- 早い段階で関係者と共有する。
- 重要な機能や優先度を明確にする。
- ユーザーテストや簡単なフィードバックを繰り返す。
- バージョン管理や注釈で変更理由を残す。
最後に一言
ワイヤーフレームは決して手間だけの作業ではありません。しっかり作ることで品質とコストパフォーマンスが向上します。初めは簡単な形から始め、段階的に精度を上げることで、安心して進められる制作体制を作れます。