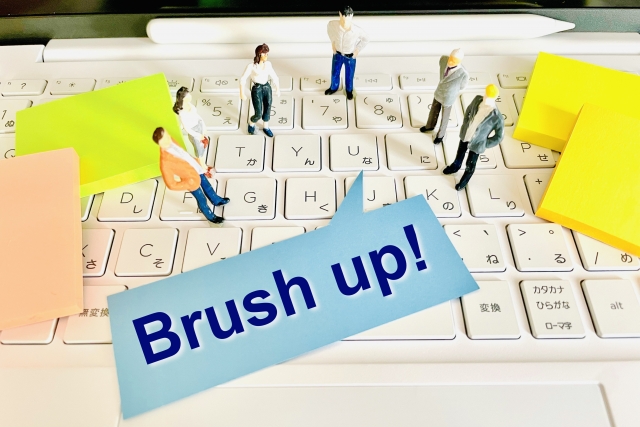はじめに
Webサイトで表示されるパンくずリスト(Breadcrumb)は、現在地の把握やサイト内の移動を助ける重要な要素です。本記事は、特にWordPressなどのCMSで表示されるパンくずリストを非表示にしたい方向けに、方法と注意点を分かりやすくまとめます。
目的
パンくずリストを非表示にする手順を具体的に示し、非表示による影響や代替案も丁寧に解説します。設定方法はテーマ別やプラグイン別、個別ページごとの対応まで扱います。
対象読者
- サイト運営者や管理者
- テーマの見た目を整えたいデザイナー
- SEOやユーザビリティに関心がある方
本記事で扱う内容(概要)
- パンくずリストの役割とメリット
- 非表示にする主な方法(CSS、PHP、プラグイン)
- 非表示にする際の注意点(SEO/ユーザビリティ)
- テーマ別や特定ページの対処法
- 実践手順のまとめ
次章から、具体的な説明を順を追って進めていきます。
パンくずリストとは?その役割とメリット
パンくずリストとは
パンくずリストは、Webサイト内の階層や現在地を矢印や「>」などでつないで示す短いナビゲーションです。ユーザーが今どのページにいるか一目でわかる表示で、サイト内を迷わず移動できるようにします。
役割
- 現在地の表示:ページがどの階層にあるかを示します。
- 上位ページへの移動:親カテゴリーやトップに戻りやすくします。
- サイト構造の可視化:サイト全体の整理された見え方を助けます。
主なメリット
- ユーザービリティ向上:訪問者が直感的に戻れるため、操作が楽になります。
- 回遊率アップ:興味のある上位カテゴリに移動しやすく、関連ページの閲覧が増えます。
- SEO効果:内部リンクが増え、検索エンジンにサイト構造を伝えやすくなります(例:商品ページからカテゴリページへリンク)。
具体例で見る使い方
- ECサイト:Home > レディース > バッグ > 商品名(商品ページからカテゴリへ戻れる)。
- ブログ:Home > レシピ > パスタ > トマトクリーム(関連記事へ移動しやすい)。
補足:表示の判断基準
サイトの規模やデザイン、運営方針で不要な場合もあります。小規模な1ページ構成では不要なことが多く、デザイン重視で見せたくない場合もあります。しかし、ユーザーの利便性とSEO効果を考えると、多くのサイトで有益な要素です。
パンくずリストを非表示にする主な方法
1. CSSで非表示にする方法
最も手軽な方法です。パンくずリストに付いているクラスやIDに対してdisplay: none;を指定します。たとえばWordPressテーマ「SWELL」では.p-breadcrumbや#breadcrumbが該当することが多いです。追加場所は「外観→カスタマイズ→追加CSS」や子テーマのstyle.cssです。
例(CSS):
.p-breadcrumb, #breadcrumb { display: none !important; }
2. テーマ設定で非表示にする方法
一部のテーマは管理画面から表示・非表示を切り替えられます。手順は一般に「ダッシュボード→外観→カスタマイズ」またはテーマ専用の設定ページを開き、パンくず表示の項目をオフにして保存します。コード不要で安全に変更できます。
3. 特定ページのみパンくずを非表示にする方法
すべてではなく特定ページだけ消したい場合、ページごとのbodyクラス(例:page-id-12)を使う方法が簡単です。該当ページにだけ効くCSSを書きます。
例(特定ページ):
body.page-id-12 .p-breadcrumb { display: none; }
また、プラグインやテーマの個別表示設定を使えば、管理画面からページ単位で制御できます。ブラウザの検証ツールで対象のクラスやIDを確認してから適用してください。
パンくずリストを非表示にする際の注意点
概要
パンくずリストを消す前に、目的と影響をはっきりさせてください。見た目をすっきりさせたい場合もあれば、特定のページで混乱を避けるために非表示にすることもあります。操作は簡単でも影響は広がります。
SEOへの影響
パンくずは内部リンクを強化し、検索エンジンにサイト構造を伝えます。例えばECサイトの「トップ > 家電 > テレビ > 商品名」のような表示がなくなると、検索エンジンがカテゴリー関係を把握しにくくなり順位に影響する可能性があります。非表示にするなら、構造化データ(schema.org)のマークアップを残すなど代替手段を検討してください。
ユーザビリティの低下リスク
利用者は自分の位置を確認しにくくなり、戻る操作や別カテゴリへの移動が面倒になります。特に階層が深いサイトでは迷いやすくなります。例:記事→カテゴリ→サブカテゴリと辿るサイトでは、パンくずがないと他の関連記事へ移動しづらくなります。
部分的非表示の注意点
一部の階層だけ非表示にすると、表示と非表示が混在してユーザーに混乱を招きます。カテゴリだけ消す、商品ページだけ消すなどは避け、方針を統一してください。
アクセシビリティと代替手段
スクリーンリーダー利用者はナビゲーションを利用します。非表示にする場合はキーボード操作や代替ナビ(サイドバーや検索)を強化してください。また、非表示は見た目だけ(CSSで隠す)であっても、構造化データやHTML上のリンクを残す方法があります。
テストと確認
非表示後はアクセス解析で離脱率や回遊率を確認し、A/Bテストで影響を測ってください。小さく変更して効果を検証すると安全です。
パンくずリストの種類と表示方法
パンくずリストは主に3種類に分かれます。以下でそれぞれの特徴と、実際の表示や非表示にする際の代表的な方法をやさしく説明します。
位置型(階層型)
- 特徴:サイトの階層構造をそのまま示します。例)ホーム > カテゴリ > サブカテゴリ > 記事
- 利点:現在地が直感的に分かるため、サイトの構造理解に役立ちます。
- 表示例:テーマが自動出力する場合が多く、HTMLで
- や
属性型(カテゴリ・タグ型)
- 特徴:カテゴリやタグなど属性ごとに分けて表示します。例)ホーム > カテゴリA > タグX
- 利点:コンテンツの分類が分かりやすく、関連コンテンツへの導線になります。
パス型(履歴型)
- 特徴:ユーザーが辿ったページの履歴を表示します。例)前のページ > 現在のページ
- 利点:訪問経路に基づくナビゲーションを提供できますが、動的なため実装はやや複雑です。
表示方法(共通の扱い)
- 見た目を消す:CSSで非表示にする方法が一般的です。例:
.breadcrumb, .breadcrumbs, nav.breadcrumb { display: none !important; }
- テーマやプラグインの違い:テーマがテンプレートで直接出力する場合はPHP側で削除する方が確実です。プラグインなら設定で非表示にできることが多いです。
- 注意点:見た目だけ消すと、構造化データ(検索エンジン向けの情報)は残る場合があります。構造化データも取り除きたい場合は、テーマやプラグインの出力箇所を確認して編集してください。
(編集は必ずバックアップを取ってから行ってください)
まとめ:パンくずリスト非表示の実践手順
以下は実際にパンくずリストを非表示にする際の手順です。順番に進めれば安全に対応できます。
- 対象を特定する
-
ブラウザの検証ツールでパンくずのHTML要素(IDやクラス)を確認します。例:
目的と技術レベルに応じて上記の方法を選び、まずバックアップと表示確認を徹底してください。