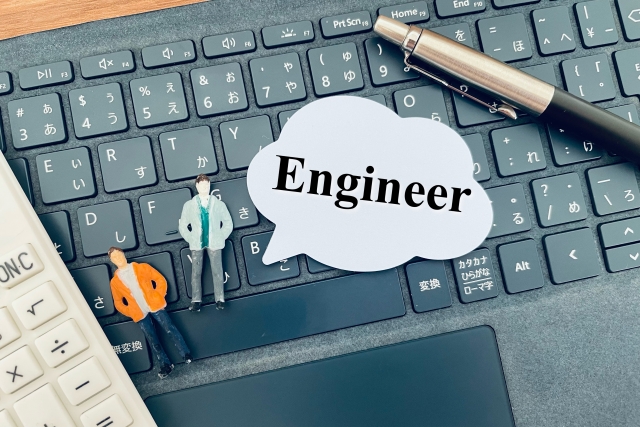はじめに
はじめに
Webサイトの構造を調べたいけれど、どこから始めればよいか迷っていませんか?この記事は、そんな疑問にお答えするために作りました。
この記事の目的
本稿では、サイト構造の基本から、SEOの観点で重要な設計、HTML解析などの技術的手法まで、実務で使える方法を丁寧に解説します。初心者の方でも段階を追って理解できるようにまとめました。
誰向けか
・サイトの改善を始めたいサイト運営者
・SEO担当者やこれから学ぶ人
・サイト監査を行う技術者やマーケター
この記事で学べること(例)
・サイトの主要構造を把握する方法
・内的リンクとURL設計の見方
・HTMLやサイトマップの基本的な読み方
・調査に便利なツールの例
次章以降で、具体的な調査手順と実践的なテクニックを順を追って説明します。読み進めることで、サイトを誰でも改善できる具体的な手順がつかめるはずです。
サイト構造とは何か
概要
サイト構造とは、Webサイト内のページやコンテンツがどのように整理され、階層やカテゴリで結びついているかを示す設計図です。見出しやメニュー、URLの階層などが含まれます。読み手にとっては道しるべ、検索エンジンにとってはコンテンツ理解の手がかりになります。
なぜ重要か
ユーザーは直感的に目的の情報にたどり着けます。例えば、料理レシピのサイトなら「トップ > レシピ > 洋食 > パスタ」のように辿れると探しやすくなります。検索エンジンは関連ページをまとめて評価しやすくなり、表示順位が向上することがあります。
主な要素
- 階層構造:トップページ→カテゴリ→個別ページ
- ナビゲーション:メニューやパンくずリスト
- URL設計:分かりやすいパス(例: /recipes/pasta)
- 内部リンク:関連ページ同士をつなぐリンク
具体例
ブログなら「カテゴリ→記事」、ECサイトなら「カテゴリ→商品一覧→商品詳細」が基本です。早く見つかる構造にすると滞在時間や回遊率が上がります。
サイト構造の調べ方・設計手順(SEO観点)
イントロ
サイト構造設計の第一歩は、ユーザーの検索意図を把握することです。検索ワードから、何を知りたいのかを分類していきます。
手順1:検索意図の収集
- キーワード例:”クレジットカード”なら「おすすめ」「悩み」「作り方」「還元率」などに分類します。
- 方法:Googleサジェストや関連キーワード、検索窓で出る候補を集めます。実際の検索結果(上位ページ)も確認します。
手順2:カテゴリ設計(ツリー化)
- 大カテゴリ→小カテゴリ→記事ページの階層で整理します。
- 例:クレジットカード(大)→還元率(小)→「高還元カード比較」の記事。
手順3:URL・階層と内部リンク設計
- URLは短く階層を分かりやすくします。カテゴリページから関連記事へ自然にリンクします。パンくずを必ず設置します。
手順4:優先順位と運用計画
- 検索ボリュームとコンバージョン価値で優先度を決め、コンテンツ作成と更新のスケジュールを立てます。
手順5:検証と改善
- サイトマップを作成し、Search Consoleやアクセス解析で効果を確認します。必要に応じてカテゴリや内部リンクを見直します。
具体的な調査方法(技術的アプローチ)
HTML/CSS/JavaScriptの役割を押さえる
HTMLはページの骨格です。見出し(h1〜h6)、段落、リンク(aタグ)、画像などの要素で構成します。CSSは見た目を決めます。ページの並びや表示の有無に影響します。JavaScriptは動的に要素を追加・変更します。たとえば、ボタンを押すと記事一覧が読み込まれる場合、JSが裏で動いています。
ソースとDOMの違いを理解する
ブラウザの「ページのソース表示(Ctrl+U)」は初回ロード時のHTMLを見せます。開発者ツール(F12)で表示するDOMは、JavaScript適用後の最終的な構造を確認できます。動的サイトはDOMで確認してください。
開発者ツールでの実践手順
- Elementsタブで見出し(h1〜h6)、nav、footer、aタグの配置を確認します。内部リンクのアンカーテキストをチェックします。
- NetworkタブでXHR/Fetchを確認し、AJAXで読み込むデータを特定します。ページが遅い場合はここを重点的に調べます。
- Consoleでエラーを確認します。レンダリングに失敗するスクリプトは構造把握を妨げます。
その他の技術的チェック項目(例)
- sitemap.xmlやrobots.txtで公開ページを把握します。
- rel=”canonical”やhreflangの有無を確認します。
- 内部リンクの巡回性(クローラビリティ)を確認するため、リンク切れを探します。
これらを順に行えば、サイトの情報設計やページ間のつながりを技術的に把握しやすくなります。
サイト構造調査・分析に役立つツール
概要
まずは「ユーザーがどんなキーワードで探しているか」を把握することが出発点です。ここでは代表的なツールと、実際の使い方・活用例を分かりやすく解説します。
Googleサジェスト/キーワードプランナー
- 使い方:検索窓に語句を入れて表示される候補や、キーワードプランナーの検索ボリュームを確認します。
- 活用例:検索候補からカテゴリ候補を洗い出し、検索ボリュームで優先度を付けることでカテゴリ設計に反映します。
競合分析・SEOツール(Keywordmap、SEARCH WRITE など)
- 使い方:競合サイトのURLやキーワードを入力して、キーワード分布や上位ページを抽出します。
- 活用例:他サイトのカテゴリ構成や内部リンクの傾向を比較し、自サイトの不足ページや統合ポイントを見つけます。
ブラウザ開発者ツール
- 使い方:ページ上で右クリック→検証(DevTools)を開き、HTML構造やmeta情報、読み込みされるリソースを確認します。
- 活用例:ヘッダー・ナビ・パンくず・構造化データの有無を素早く確認し、実際のページ構成を可視化します。
クローラー系ツール(Screaming Frog 等)
- 使い方:サイト全体をクロールしてURL一覧、ステータスコード、内部リンク数、title・metaを出力します。
- 活用例:サイトの浅い/深い構造を把握し、重複や孤立ページを発見して構造改善に繋げます。
使い方の流れと注意点
- 小さいキーワード群を拾い、カテゴリごとにまとめてから優先順位を付けます。
- 複数ツールでデータを突き合わせると精度が上がります。
- 一つのツールだけに頼ると見落としが出やすいので、目的に合わせて使い分けてください。
サイト構造設計・調査のポイント・注意点
1) ユーザーのニーズを最優先に
サイト構造は検索エンジン向けでなく、まず訪問者が直感的に目的を達成できることを基準に設計します。例:商品の購入導線なら購入ボタンやカテゴリへ最短でたどり着けるか確認します。
2) 階層は浅くシンプルに
過度に深い階層は避け、主要ページは3クリック以内で到達できるようにします。階層を減らすと内部リンクも自然になり、迷わない構成になります。
3) 分かりやすいナビと内部リンク
グローバルナビやパンくずで現在地を示します。関連コンテンツへの内部リンクは文脈に合う場所に設置し、ユーザーの回遊を促します。
4) URL・重複・リダイレクトの注意
意味が分かる短いURLを使い、同じ内容が複数URLで存在しないようにします。ページ移動時は適切にリダイレクトを設定してリンク切れを防ぎます。
5) 変更時の影響確認とテスト
構造変更前にアクセス解析で主要ページを特定し、変更後はトラフィックやコンバージョンを比較します。A/Bテストやステージング環境での確認がおすすめです。
6) 定期的な見直しと関係者共有
ユーザー行動や検索需要は変わるため、半年~1年ごとに見直します。変更は運用チームや編集者と共有し、影響範囲を把握して進めます。
チェックリスト(短め)
– 主要導線は直感的か
– 階層は浅いか
– 重複や404はないか
– 変更の影響を測定しているか
これらを習慣化すると、使いやすく強いサイト構造になります。
まとめ
サイト構造の調査・設計は、ひとつひとつの工程を順に進めることで結果が出ます。本章では要点をわかりやすくまとめ、実務で使えるチェックリストと次の一手をお伝えします。
重要な流れ(基本)
- 検索意図の分析:ユーザーが何を知りたいかを明確にする
- カテゴリ分け:テーマごとに論理的に分類する
- ページ設計:各ページの役割とコンテンツを決める
- HTML・技術解析:URL・内部リンク・メタ情報・速度などを最適化する
成功のポイント
- SEOとUXの両方を意識して情報設計すること
- 一貫したURLとパンくず、内部リンクで導線を作ること
- モバイルや表示速度、構造化データも忘れずに対処すること
実務チェックリスト
- 主要検索ワードとユーザー意図を整理したか
- カテゴリとナビゲーションは直感的か
- 重要ページに適切な内部リンクがあるか
- サイトマップ・canonical・リダイレクトを整備したか
- 効果測定(PV、直帰率、検索順位)を設定したか
次の一手
まずは小さな改善から始め、アクセスと検索順位を定期的に確認してください。問題が見つかれば仮説を立てて検証を繰り返すことで、より良いサイト構造が作れます。