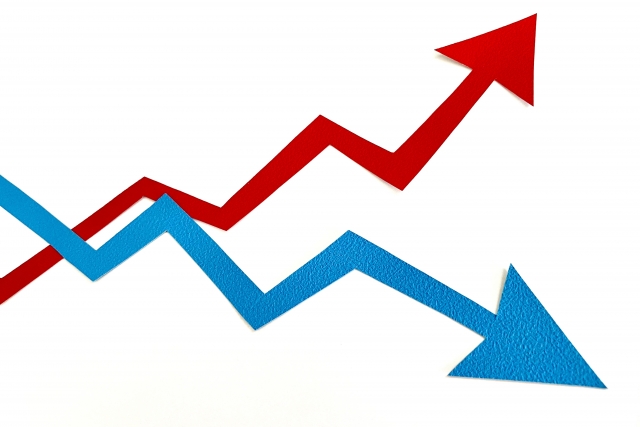はじめに
今抱えていませんか?
「検索からの訪問が増えない」「どのページが読まれているか分からない」――そんな悩みをもっていませんか?この書籍(ガイド)では、Googleサーチコンソールの基本から実践的な使い方まで、やさしく丁寧に解説します。初心者の方でも迷わず始められるよう具体的な例を交えて説明します。
この章の目的
本章はガイドの導入部分です。サーチコンソールを学ぶ意味や、本書で得られることをわかりやすく示します。まず全体像をつかんで、次の章へスムーズに進めるようにします。
誰に向いているか
サイト運営を始めたばかりの方、アクセス改善を目指す個人ブロガーや中小事業者、基本を整理したい中級者に向けています。専門用語は最小限にし、実例で補足します。
本書の読み方
各章は「何ができるか」「どの画面を見るか」「具体的に何を改善するか」の順で説明します。まずは全体をざっと読んでから、気になる章を詳しく読むと効率的です。
読み終えたあとにできること
- 自分のサイトで重要な指標を確認できる
- 検索の問題点を見つけて優先順位をつけられる
- 改善のための具体的な第一歩を踏み出せる
これから一緒に、検索からの訪問を増やすための基本を学んでいきましょう。
Googleサーチコンソールとは何か
概要
Googleサーチコンソール(以下、サーチコンソール)は、Googleが無料で提供するウェブサイト管理ツールです。サイトがGoogle検索でどう見えているかを示し、検索からの表示回数やクリック数、掲載順位などの実データを確認できます。サイト運営やSEO対策に直接役立つ公式ツールです。
主な機能(簡単な例つき)
- 検索パフォーマンス確認:ある記事が「レシピ 簡単」で何回表示され、何回クリックされたかが分かります。
- インデックス管理:新しいページをGoogleに登録するよう依頼したり、登録状況を調べます。
- URL検査:個別ページのインデックス状況やモバイルでの表示問題を確認します。
- リンク確認:どのサイトからリンクを受けているかを把握できます。
- 問題通知:クロールエラーや手動による対策、セキュリティ問題の通知を受け取れます。
誰が使うべきか
ブログ運営者、小規模事業者、ウェブ担当者、SEOを学ぶ人など、検索流入を増やしたい全ての人に向きます。専門知識がなくても基本的な操作は直感的です。
導入の流れ(簡単)
- サイト所有権の確認(HTMLタグやドメイン認証など)
- サイトマップの送信
- パフォーマンスやカバレッジのレポートを定期確認
注意点
データは数日遅れて表示されます。個々の訪問者行動は分からないため、Googleアナリティクス等と併用すると効果的です。
サーチコンソールでできること一覧
検索パフォーマンスの確認
検索結果での表示回数・クリック数・CTR(クリック率)・平均掲載順位を確認できます。例えば「特定の検索語で表示は多いがクリックが少ない」ページを見つけ、タイトルや説明文を改善する、といった具体的な対策に使えます。
インデックス管理とURL検査
各ページがGoogleにインデックスされているかを調べ、問題があれば再送信できます。新しい記事を公開したらURL検査でインデックス登録をリクエストする、といった作業ができます。
リンク状況の把握
外部サイトからの被リンクと、自サイト内の内部リンクを確認できます。どのページが多くリンクされているか分かるので、重要ページの強化や内部リンクの最適化に役立ちます。
サイトの問題点・エラー検知
カバレッジ(インデックス登録の可否)、クロールエラー、モバイルの使い勝手の問題などを通知します。エラー箇所を直してから再検査を依頼できます。
ページエクスペリエンスとモバイル対応
Core Web Vitals(表示速度や視覚の安定性)やモバイルユーザビリティの状況を確認できます。たとえばLCPが遅ければ画像最適化や遅延読み込みで改善できます。
リッチリザルト・セキュリティ監視
構造化データの問題やリッチリザルトの表示状況、手動ペナルティやセキュリティ警告(マルウェア等)も確認できます。問題が出たら修正して再審査を申請できます。
検索パフォーマンスの分析
はじめに
検索パフォーマンス画面では、検索語(クエリ)ごとの表示回数・クリック数・平均掲載順位・CTR(クリック率)を確認できます。どのキーワードで流入があるか、どのページがクリックされているかを把握し、改善点を見つけます。
主要指標の見方
- 表示回数:検索結果に表示された回数。需要の高さを示します。例:表示が多ければ注力の価値あり。
- クリック数:実際にユーザーがクリックした回数。興味の度合いを表します。
- CTR(クリック率):クリック数÷表示回数。タイトルや説明文(スニペット)の魅力を評価できます。
- 平均掲載順位:平均的な検索結果の位置。順位改善で流入が増えます。
クエリとページ別の分析方法
クエリ別でどんな言葉が来ているか、ページ別でどのページがクリックされているかを照らし合わせます。例:あるクエリは表示多いがCTR低い場合、タイトルやメタ説明の改善でクリック増を狙います。逆にCTR高く順位が低いなら、コンテンツを強化して上位を目指します。
フィルタ・比較で深掘り
期間、デバイス(モバイル/PC)、国、検索タイプ(ウェブ/画像)で絞り込みます。モバイルでCTRが低ければページ表示速度や見え方を改善します。
改善アクションの優先順位
- 表示多くCTR低い:まずタイトル・説明を改善
- 表示多く順位低い:コンテンツ強化・内部リンク
- 表示少ないがCTR高い:関連キーワードでコンテンツ拡張
運用のコツ
定期的にレポートを確認し、CSVでエクスポートして傾向を比較します。小さな改善を積み重ねれば、検索からの流入が着実に増えます。
インデックス管理とURL検査
URL検査とは
URL検査は、個別ページがGoogleにどのように見えているかを確認できる機能です。インデックスの有無やクロールの状況、エラー内容、正規化(canonical)の扱いなどを細かく確認できます。
URL検査の使い方(具体例)
- 検査欄に対象のURLを入力して実行します。
- 「URLはGoogleに登録されています」かどうかを確認します。未登録なら「インデックス登録をリクエスト」で申請できます。
- ライブテストで実際のレンダリングやモバイル表示も確認できます。新規ページを公開したらリクエストしておくと早めに反映されることが多いです。
よくあるエラーと対処
- noindexタグが付いている:該当タグを削除して再検査します。
- robots.txtでブロックされている:許可する設定に変更します。
- サーバーエラー(5xx):サーバーの復旧や設定を確認します。
- 重複や誤ったcanonical:正しいURLをcanonicalに指定します。
サイトマップ送信
サイトマップ(sitemap.xml)を送信すると、Googleがページを見つけやすくなります。重要なページをまとめて伝えられます。 ただし、送信で必ず即時インデックスされるわけではありません。
インデックスを早めるコツ
- 重要ページは内部リンクで目立たせる
- 更新があれば再リクエストする
- サイトマップを整備しておく
これらを習慣にすると、インデックス管理が安定します。
リンク状況の把握
はじめに
リンクレポートは、外部サイトからの被リンクや自分のサイト内の内部リンクを一覧で確認できる機能です。SEOで重要なポイントを見つけるのに役立ちます。
外部リンク(被リンク)の見方
- リンク元サイト:どのドメインからリンクされているか分かります。
- 被リンク数:サイト全体や各ページへ向かうリンク数が分かります。
- アンカーテキスト:リンクに使われた文言が確認できます。
例:雑誌サイトからのリンクが多ければ、その記事の評価が高い可能性があります。
内部リンクの確認
- リンク先ページごとの内部リンク数を見て、重要ページに十分リンクが集まっているか確認します。
- 内部リンクが少ないページは、サイト内で目立たず検索順位が伸びにくい傾向があります。
例:人気記事Aに内部リンクが集中していれば、関連する記事Bにもリンクを張り巡らせます。
活用のポイント
- 質の高い被リンクを見つけたら、同じようなサイトへ露出を増やす施策を検討します。
- アンカーテキストに偏りがないかチェックして、自然な表現を促します。
- 明らかにスパムと思われるリンクは慎重に扱ってください。誤った対処は逆効果になることがあります。
実践例
- サーチコンソールで「リンク」→「外部リンク」を開く。
- 上位のリンク元を確認し、関連するサイトへアプローチする。
- 「内部リンク」で各ページのリンク数を確認し、少ないページへ内部リンクを追加する。
これらの手順でリンク状況を把握し、サイトの評価向上につなげてください。
サイトの問題点・エラー検知
この章では、Search Consoleで見つかるサイトの問題点とその対処法をわかりやすく解説します。
カバレッジ(インデックス状況)
インデックス登録されているか、未登録かを確認します。未登録の理由は「404(存在しない)」「noindex」「robots.txtでブロック」などです。例えば、削除したページに外部リンクが残ると404が増えます。対応は、不要なら放置でもよいですが重要ページならリダイレクトやnoindexの解除、再送信を行います。
エラーと警告
サーバーエラー(5xx)、ソフト404、モバイル表示の問題、構造化データの警告などが出ます。構造化データの警告はリッチ表示に影響します。まずは再現して原因を特定し、修正後にURL検査で再クロールを依頼します。
手動対策とセキュリティ問題
手動対策(ペナルティ)はSearch Consoleで通知されます。スパム行為や不自然なリンクが原因です。通知を受けたら問題を直して再審査リクエストを出します。マルウェアやフィッシングなどのセキュリティ問題も同様に即対応し、再確認を依頼してください。
優先順位と対応の流れ
優先度は「セキュリティ・手動対策>サーバー障害・大量のクロールエラー>個別の404や警告」です。対応手順は、(1)問題の特定、(2)修正、(3)URL検査や再審査の送信、(4)経過観察です。
Search Consoleのメール通知を有効にし、定期的にカバレッジとメッセージを確認しましょう。早めに対処すると検索順位の低下リスクを減らせます。
ページエクスペリエンス・コアウェブバイタル・モバイル対応
ページエクスペリエンスとは
ページエクスペリエンスは、訪問者がページを快適に使えるかを示す指標です。表示速度や操作のしやすさ、広告やレイアウトの邪魔がないかなどを総合的に評価します。
コアウェブバイタルの主な3指標
- LCP(Largest Contentful Paint):ページの主要な部分が表示されるまでの時間。目安は2.5秒以内。例:記事本文の画像や見出しが早く出るか。
- FID(First Input Delay):最初の操作に対する応答時間。短いほど良い。タップしても反応が遅いと評価が下がります。
- CLS(Cumulative Layout Shift):表示中のズレの量。突然広告で文章が動くと数値が悪化します。
モバイル対応の確認ポイント
- ビューポート設定、フォントやボタンのサイズが適切か
- タップ要素同士が近すぎないか
- 画像やリソースがスマホ向けに最適化されているか
サーチコンソールでの使い方と改善の始め方
サーチコンソールの「ページエクスペリエンス」レポートで問題を確認できます。具体的なURLや影響範囲が表示されるので、まず影響の大きいページから下記を試してください。
– 画像の圧縮、遅延読み込み
– 不要なスクリプトの削除や遅延実行
– レイアウト固定のためのサイズ指定(画像・広告)
これらを順に改善すると、ユーザー満足度と検索評価の両方が向上します。
リッチリザルト・拡張機能の確認
概要
拡張(Enhancements)では、FAQやパンくずリストなどのリッチリザルトが正しく表示されているか、エラーがないかを確認できます。構造化データの問題点を見つけ、表示改善につなげるのに役立ちます。
表示状況の確認方法
- サーチコンソール左側メニューの「拡張」から該当の項目(FAQ、パンくずなど)を選びます。
- 「有効」「無効」や「警告」の状態が一覧で見えます。クリックすると該当URLの一覧が出ます。
- 個別ページは「URL検査」で詳しく調べられます。実際の検索結果プレビューも確認可能です。
エラーの見方と対処
よくあるエラーは「必須プロパティが欠けている」「値の形式が違う」「重複したマークアップ」です。対処の手順は次の通りです。
– 該当ページの構造化データを修正(例:JSON-LDで必須項目を追加)。
– 修正後に「URL検査」で再テストし、問題が消えたらインデックス登録をリクエストします。
最適化のポイント(実務的な注意)
- JSON-LD形式を使うと管理しやすくなります。
- ユーザーに見える内容だけをマークアップしてください。見えない情報をマークアップすると否認されることがあります。
- FAQは質問・回答をペアで、パンくずは階層と各項目のURLを正確に設定します。
運用のコツ
拡張レポートは定期的に確認しましょう。サイト更新やテンプレート変更のたびに構造化データが崩れることがあります。エラーを見つけたら速やかに修正し、再検査を行う習慣をつけると効果的です。
サイト改善への活用方法
はじめに
Search Consoleのデータを改善の材料に変えるには「観察→仮説→実行→検証」の流れが大切です。ここでは具体的な手順と例を挙げて実践しやすく説明します。
1. 優先順位をつける
まず検索パフォーマンス画面で、クリック数・表示回数・CTR(クリック率)を確認します。例えば「表示は多いがCTRが低いページ」はタイトルや説明文(メタディスクリプション)を見直す優先度が高いです。逆に「クリックはあるが滞在時間が短いページ」は本文の改善や内部リンク強化を検討します。
2. コンテンツ改善の具体例
・検索意図に合っていない箇所を追記する(Q&Aや見出し追加など)
・タイトルを20〜30文字程度で魅力的にする
・構造化データを追加してリッチ表示を狙う
これらは少ない工数で効果が出やすい対策です。
3. 技術的な問題の修正
URL検査やカバレッジでエラーを見つけ、優先的に直します。モバイル表示崩れや遅い読み込みは離脱につながります。画像最適化や不要なスクリプト削除で改善できます。
4. 効果検証と運用ルール
変更後はSearch Consoleで検索キーワードやページごとのクリック数を数週間追い、変化を確認します。改善が見られない場合は仮説を修正して再実行します。したがって小さな改善を継続する姿勢が重要です。
5. 実務のチェックリスト(短期〜中期)
・上位表示だがCTR低いページの洗い出し
・低滞在の主要ページの内容補強
・カバレッジのエラー解消
・モバイルと表示速度の改善
・実施後の効果記録(週次または月次)
これらを習慣化すれば、検索流入の増加やコンバージョン向上につながります。初心者でも順序立てて進めれば着実に成果が出せます。
Googleアナリティクスとの違い
概要
サーチコンソールは「検索でどう見られているか」を中心にデータを出します。一方、Googleアナリティクス(GA4)は「サイト内でユーザーがどう動いたか」を計測します。目的が違うため、役割を分けて使うと効率的です。
主な違い(わかりやすい比較)
- サーチコンソール:検索クエリ、表示回数(インプレッション)、クリック数、平均掲載順位、インデックス状況。例)あるキーワードで多く表示されるがクリック率が低いことが分かる。
- GA4:ユーザー数、セッション、ページ滞在時間、イベント(ボタン押下、購入など)、コンバージョン。例)検索から来たユーザーがフォームを送信したか確認できる。
具体的な使い分け例
- 検索での改善点を見つける:サーチコンソールで「表示は多いがCTRが低い」ページを探す。見つけたら、タイトルやディスクリプションをGA4で流入後の行動を確認しつつ改善します。
- コンバージョン最適化:GA4で離脱の多いページを特定し、該当ページの検索クエリをサーチコンソールで確認して流入意図とギャップを埋めます。
連携と実務の流れ
- 両方を導入してプロパティをリンクする(設定で連携可能)。
- サーチコンソールで検索上の課題を洗い出す(例:高順位だがCTRが低い)。
- GA4でそのページの行動指標とコンバージョンを確認し、改善案を実施する。
注意点
- 指標の定義が違うため数値は完全には一致しません(クリック数とセッションは同じではない)。
- データの更新タイミングやサンプリングで差が出ることがあります。
まとめとおすすめの使い方
はじめに
本書で扱ったGoogleサーチコンソールは、初心者から中級者まで必ず活用すべきツールです。検索の見え方や問題点を直接確認できるため、サイト運営に役立ちます。
まず使うべき機能(最初の一歩)
- 検索パフォーマンス:流入キーワードや表示回数を確認し、改善対象ページを見つけます。
- URL検査:個別ページのインデックス状況や問題を即確認できます。
- サイトマップ送信:新規ページの検出を早め、インデックス促進に有効です。
段階的な習得法
- 週に一度、検索パフォーマンスを見て上位ワードと低CTRページを抽出します。
- URL検査で問題を特定し、優先度の高い修正から対応します。
- モバイル対応やコアウェブバイタルの改善、リッチリザルトの確認へ進みます。
日常チェックリスト(簡単)
- 毎週:検索パフォーマンスとエラー確認
- 月次:サイトマップ再送信、主要ページのインデックス確認
- 修正後:再クロール依頼で反映を待ちます
注意点
- ひとつの指標に頼りすぎないこと。複数のデータを組み合わせて判断してください。
- 変更の反映は時間がかかることがあります。短期の変動を過剰に評価しないでください。
最後に、小さな改善を積み重ねることで確実に成果が出ます。まずは紹介した基本機能から始め、徐々に他の機能も習熟していきましょう。