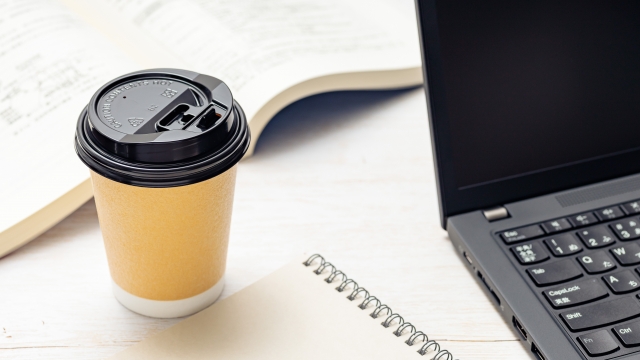はじめに
目的
この章では、本書の狙いと読み方を簡潔に示します。本書は、Google Analytics 4(GA4)での「直帰率」について、確認方法や定義の違い、平均値の目安、改善に使える視点までを分かりやすく解説するガイドです。初めてGA4に触れる方から、UA(ユニバーサルアナリティクス)から移行した方まで役立つ内容を目指しています。
読者想定
- 自社サイトやブログのアクセス解析をはじめた方
- UAからGA4に移行したが、指標の違いで戸惑っている方
- 直帰率を改善してページの質を高めたい方
本書のポイント
- 専門用語は必要最小限に抑え、具体例を交えて説明します。
- GA4では直帰率が標準レポートに表示されない点を重要視し、実際の確認手順やカスタマイズ方法を丁寧に紹介します。
- 数字の見方だけでなく、改善につなげる考え方も扱います。実務で使える視点を重視しています。
読み方の目安
まず本章で全体像をつかみ、次章以降で「定義」「確認方法」「改善」の順に読み進めると理解しやすいです。各章は独立して読むこともできますので、気になる章だけ参照していただいても構いません。
GA4の直帰率とは?従来との違い
直帰率(従来の考え方)
直帰率とは、ユーザーが最初に開いたページだけを見て他のページに移動せず離脱した割合を指します。たとえば、ブログ記事を1ページだけ読んでブラウザを閉じる場合は直帰となります。分かりやすい指標で、ページの「入口での離脱」を示します。
GA4での定義の変化
GA4では標準レポートに従来の直帰率が表示されず、新しい指標「エンゲージメント率」が導入されました。GA4での直帰率は明示的な標準値ではなく、「エンゲージメントのなかったセッションの割合」として再定義されます。具体的には、セッションがエンゲージメント条件(10秒以上の滞在、コンバージョン、または2ページ以上のビューなど)を満たさない場合、そのセッションは“直帰”として扱われます。
実務上の違いと注意点
- 数値が変わる:従来の直帰率と単純に比較すると誤解を招きます。GA4は滞在時間やイベントを重視するため、直帰率が低く出ることがあります。
- 指標の見方を変える:ページの品質を測る際は、直帰率だけでなくエンゲージメント率や特定イベント(スクロール、クリック、動画再生)を合わせて見ると実態がつかめます。
- 単ページサイトやLPでは違いが大きく出る可能性があります。必要ならGA4でカスタム指標を作り、従来の振る舞いに近い形で計測することもできます。
読者の行動を正しく理解するために、GA4では“見方”を少し変えて分析することをおすすめします。
GA4で直帰率を確認する場所・手順
ここでは、GA4で直帰率を見つけるための具体的な操作手順を、レポート画面と探索レポート(自由形式)の2通りでわかりやすく説明します。初めての方でも迷わないよう、画面の場所や注意点も補足します。
レポート画面での確認方法
- Google Analyticsにログインし、対象のGA4プロパティを開きます。
- 左側メニューの「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」を選択します。
- 画面右上の鉛筆アイコン(編集)をクリックしてレポートカスタマイズ画面に入ります。
- 「指標」→「指標を追加」から「直帰率」を選択し、見やすい位置に移動して「適用」します。
- これでページごとの直帰率や全体傾向を確認できます。期間を上部で変更すると比較もしやすくなります。
探索レポート(自由形式)での確認方法
- 左側メニューの「探索」→「自由形式」を選びます。
- 右側の指標欄で「+」をクリックし、「直帰率」をインポートします。
- ディメンション(例:ページ、ランディングページ、流入経路)を追加します。流入元ごとの直帰傾向も見られます。
- 「値」欄に直帰率をドラッグ&ドロップして表やグラフを作成し、必要に応じてフィルタやセグメントを設定します。
ポイント:よく使う表示は保存しておくと次回から簡単です。直帰率だけで判断せず、平均滞在時間やコンバージョンも合わせて見ると精度が上がります。
直帰率の平均・目安
平均的な目安
一般的には直帰率は40%〜60%がよく見られるレンジです。ただし、この数値だけで良し悪しを判断しないでください。ページの目的や訪問者の行動によって適正値が変わります。
業界・サイトタイプ別の目安
| 業界・サイトタイプ | 直帰率の目安 |
|---|---|
| eコマース(小売) | 20%〜40% |
| 情報サイト(ブログ等) | 50%〜70% |
| B2B サービスサイト | 30%〜50% |
| ランディングページ | 70%〜90% |
| 飲食店・ローカルビジネス | 30%〜50% |
目安の見方と具体例
ランディングページは問い合わせや申し込みを促すため、訪問の多くが達成または離脱で直帰率が高くなりやすいです。一方、商品一覧やECの閲覧は他ページへ遷移するため直帰率が低めになります。
高い直帰率が必ずしも問題ではありません。例えば問い合わせフォームを設置したランディングページで、訪問者の多くがフォーム送信で完了していれば直帰率が高くても目的達成と言えます。
判断のポイント
- ページの目的(情報提供/購入/申込)を基準にする
- 同業他社や過去の自サイト値と比較する
- 平均値から大きく外れる場合は、導線・コンテンツ・読み込み速度を確認する
これらを踏まえて、直帰率は参考値として扱い、目的達成の視点で評価してください。
直帰率と離脱率の違い・注意点
直帰率(Bounce Rate)とは
サイトに来て最初のページだけ見て何もせずに離れたセッションの割合です。例えばブログ記事を開いてすぐタブを閉じたケースが該当します。ランディングページの“第一印象”を測る指標です。
離脱率(Exit Rate)とは
特定のページがそのセッションの最後に見られた割合です。ユーザーが複数ページを見た後、最後に閲覧したページがどれかを示します。購入完了ページの離脱率が高ければ、次の導線を検討します。
GA4での扱いと注意点
GA4はイベント中心の仕様で、従来の指標の意味合いが変わります。直帰率はデフォルトで重視されず、「エンゲージメント率(滞在や操作が基準)」を見て逆算する形が一般的です。探索レポートでは、直帰率や離脱率を自由に算出できます。
注意点:
– UA(従来版)との数値は直接比較できません。定義が変わっています。
– シングルページでも「滞在時間やイベントが発生すると直帰扱いにならない」点に注意してください。
– フィルタやセグメントで値が大きく変わることがあるため、条件を揃えて比較しましょう。
どちらを見るべきか
ランディングページの改善には直帰率、ページ遷移や離脱ポイントの特定には離脱率が役立ちます。両方を組み合わせて原因を探ると効果的です。
直帰率を活用した改善視点
直帰率を活用した改善視点
なぜ直帰率を見るのか
直帰率が高いと、訪問者がページを開いてすぐ離れていることを示します。改善の優先度を決めるために、まず「目的(購入、資料請求、記事閲覧など)」と照らし合わせて評価します。
主な改善ポイント
- ページ内容の見直し:タイトルや導入文で期待と実際の内容が合っているか確認します。例:検索ワードで来ているのに違う情報なら離脱します。
- 導線(ナビゲーション):次に何をすればいいか分かる導線を作ります。関連リンクや目立つボタンを配置しましょう。
- CTA(行動喚起)の最適化:ボタン文言や色、設置場所を変えて反応を測ります。短く具体的な文言が有効です(例:「無料で試す」「資料をダウンロード」)。
- ページ速度の改善:表示が遅いと離脱します。画像最適化や不要なスクリプトの削減を検討します。
- ユーザー意図とコンテンツの一致:検索キーワードや参照元ごとにコンテンツを調整します。期待に沿った情報があるかを確認します。
- モバイル対応:スマホで見にくいと直帰が増えます。レイアウトやフォント、クリックしやすさをチェックします。
データを使った具体的な進め方
- セグメント分析:流入元(検索、SNS、広告)やデバイス別で直帰率を比べます。問題のある流入元を特定します。
- エンゲージメント率との併用:直帰率だけで判断せず、エンゲージメント(滞在時間やイベント)も見ます。滞在時間が長ければ直帰していても価値がある場合があります。
- 仮説→改善→計測のサイクル:小さな変更(見出し、CTA、画像)を行い、A/Bテストや比較で効果を測ります。期間は最低数週間を目安にします。
改善の優先順位の付け方
影響が大きく工数が小さいもの(例:CTA文言、画像差し替え)から取り組みます。効果が不明な場合はテストを行い、データで判断します。
注意点
直帰率は単体で見ると誤解を招くことがあります。必ず他の指標と合わせて判断してください。
まとめ
ここまでで、GA4における直帰率の確認方法と活用の基本を解説しました。
-
GA4では標準レポートをカスタマイズするか、探索レポート(自由形式)で「直帰率」を指標に追加して確認します。具体例として、特定のページだけを絞って直帰率を見れば、改善優先度がわかります。
-
直帰率の数字は業界やページの目的で変わります。Eコマースの購入完了ページとブログ記事では目安が違うため、同じ基準で判断しないでください。過去の自サイトデータや同業他社の傾向を参考にします。
-
分析の流れはシンプルです。直帰率が高いページを見つけ → ユーザー行動(滞在時間、イベント発火)を確認 → 原因を仮説化 → 小さな改善(見出しや導線、読み込み速度の改善、CTAの明確化)を実施 → 結果を計測します。A/Bテストやイベント設定で効果を検証すると成果が見えやすくなります。
最後に、直帰率は単独で善し悪しを判断する指標ではありません。他の指標と組み合わせて、ユーザーの行動を丁寧に見ていくことが大切です。