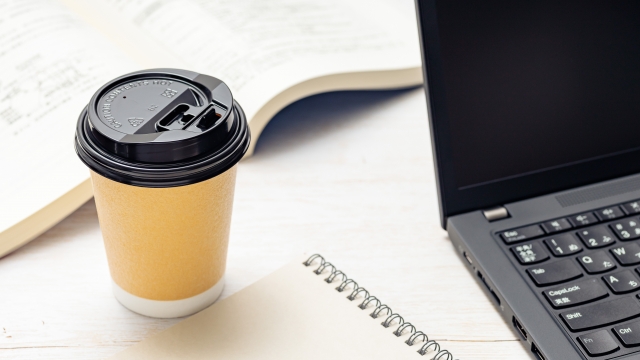はじめに
ブログ記事の導入文
「CMS(コンテンツ管理システム)の要件定義書をどう作ればいいかわからない」「関係者の合意が取りづらい……」という悩みをもっていませんか?本記事は、CMS要件定義書の目的や書くべき項目、具体的な例、作成の流れなどをやさしく解説します。この記事を読めば、要件定義書の全体像がつかめ、次の一歩を迷わず進められるようになります。
本記事の目的
CMS導入やリプレイス時に必要な要件を整理し、関係者間で認識を合わせることが目的です。仕様の抜けや誤解を減らし、開発や導入の手戻りを防ぎます。
誰に役立つか
- プロジェクトマネージャー
- コンテンツ担当者やマーケティング担当
- 開発ベンダーとの調整を行う方
具体例:社内情報を公開するイントラサイトや、商品紹介中心のコーポレートサイトなどの担当者に向いています。
この記事の使い方
章ごとに読み進め、後半のテンプレートやサンプルを参考に実際の要件定義書を作成してください。要点を押さえれば、関係者との合意形成がスムーズになります。
CMS要件定義書とは何か
定義
CMS要件定義書は、CMS(コンテンツ管理システム)導入や開発で必要な機能や仕様を文書で明確にするものです。誰が何を使って、どのように運用するかを具体化します。
目的
目的は関係者の認識をそろえることです。発注者、開発者、運用担当が同じゴールを共有し、品質・納期・コストの管理を容易にします。例えば、記事の投稿権限やバックアップ頻度といった運用ルールも明記します。
主な利用者
- 発注者(要望の提示)
- 開発者(実装の指針)
- 運用担当(運用手順の基礎)
含まれる項目(代表例)
- 機能要件(編集、公開、承認フローなど)
- 非機能要件(性能、セキュリティ、可用性)
- 運用・保守条件(バックアップ、権限管理)
メリット
要件を文書化すると、誤解や手戻りを減らせます。結果として開発コストと納期の安定につながります。
要件定義書に記載すべき主な項目
以下はCMSの要件定義書に最低限盛り込むべき項目と、その書き方のポイントです。目的は関係者の認識を揃え、実装・運用での齟齬を防ぐことです。
システム概要・目的
- 導入背景:例)更新負荷が高く、担当者が分散している。
- 目的:例)更新効率化、ブランド一貫性の維持。
- 全体像:フロント、CMS本体、DB、外部APIの構成図を入れる。
- 用語定義:記事、テンプレート、モジュール等を明確にする。
業務要件
- 対象業務:どのサイト/ページをCMSで管理するか。
- 運用フロー:作成→レビュー→承認→公開の手順と担当者。
- 現状課題:承認遅延や重複作業などと改善目標(KPI)。
機能要件
- ページ・コンテンツ管理、WYSIWYG/ブロックエディタ
- ユーザー管理・権限(編集者、承認者、公開者)
- 検索・フィルタ、タグ管理
- メディア管理(画像・動画、自動最適化)
- 多言語対応、公開スケジュール、API連携、アクセス解析連携
(各機能は利用シナリオと画面例を添えると分かりやすい)
非機能要件
- 性能:同時アクセス数、応答時間目標
- セキュリティ:認証方式、ログ、脆弱性対応
- 保守・運用:バックアップ頻度、障害時対応、SLA
- インフラ:クラウド/オンプレ、SSL、監視要件
SEO・マーケティング要件
- meta/ogタグ編集、構造化データの出力
- タグ管理(GA/GTM等)の実装、目標設定
- ABテストやキャンペーン機能の必要性
進行・開発・運用体制
- 体制図:PM、開発、デザイナー、コンテンツ担当の役割
- スケジュール:マイルストーン(要件確定、実装、検証、リリース)
- リリース後の保守体制と連絡フロー
その他
- テスト計画(単体、結合、受入)
- リリース計画とロールバック手順
- ドキュメント一覧:要件書、設計書、運用マニュアル
これらを具体的に書き出すことで、設計や開発、運用時の認識差を減らせます。
CMS要件定義書サンプル構成例(目次例)
以下はCMS要件定義書の見出し例と、各項目で記載すべきポイントです。読み手が目的を理解しやすい順で並べています。
- はじめに(目的・背景)
-
導入の目的、期待する効果、対象範囲を明確に記載します。
-
現状の課題・現状分析
-
現行サイトや運用の問題点、改善したい業務フローを具体的に示します。
-
システム全体構成図
-
全体の構成図や関係システム、データの流れを図で示します。
-
用語定義
-
曖昧さを避けるため、主要用語や略語の定義をまとめます。
-
業務要件
-
業務上必要な機能や担当者の役割、運用ルールを記載します。
-
機能要件
-
機能一覧、各機能の詳細、画面や入出力仕様を具体的に書きます。
-
非機能要件
-
性能要件(レスポンスや同時接続数)、セキュリティ、運用性、インフラ要件を含めます。
-
コンテンツ・サイトマップ要件
-
ページ構成、コンテンツ管理方法、テンプレート要件を整理します。
-
SEO/マーケティング要件
-
メタ情報、URL設計、解析ツール連携、運用方針を記載します。
-
制作・開発要件
-
デザイン指針、コーディング基準、外部連携仕様やAPI要件。
-
テスト・リリース要件
-
テスト項目、受入基準、リリース手順とロールを明示します。
-
運用・保守要件
-
障害対応、バージョン管理、バックアップや監視の運用ルール。
-
予算・スケジュール
-
概算費用、マイルストーン、リソース見積もりを記載します。
-
付録(参考資料・用語集等)
- 関連資料、詳細設計へのリンク、用語集を添えます。
この目次をベースに、プロジェクトの規模や関係者に合わせて項目を追加・調整してください。
CMS機能要件の記載例とポイント
概要
CMSの機能要件は「大項目→中項目→小項目」の階層で整理します。各機能に対して目的、概要、ユーザー操作シナリオ、画面遷移、入力/出力項目、エラー時の挙動を具体的に記載します。
記載の階層構成
- 大項目:ページ管理、ユーザー管理、メディア管理など
- 中項目:新規作成、編集、削除、公開設定など
- 小項目:バリデーション項目、ボタン配置、確認ダイアログ、ログ記録など
記載例(ページ管理)
目的:公開ページを作成・編集・公開する
概要:WYSIWYGで編集、下書き保存、公開日時予約
ユーザーシナリオ:編集者が記事を作成→プレビュー→公開予約
入力項目:タイトル(必須)、本文(HTML)、公開日時(任意)
出力項目:公開URL、公開ステータス
エラー挙動:タイトル未入力は保存不可、アップロード失敗時は再試行メッセージ
記載例(ユーザー管理)
目的:編集権限を管理する
概要:ユーザー作成、権限割当、パスワードリセット
シナリオ:管理者がユーザーを作成→権限を割当→招待メール送信
記載例(メディア管理)
機能:ファイルアップロード、検索、メタ情報編集
入力:ファイル、キャプション、代替テキスト
エラー:容量超過は拒否、対応形式でない場合は警告
多言語・解析連携
多言語:翻訳元・翻訳ステータス、言語切替UI
解析連携:Google Analytics等へのイベント送信項目、計測タイミング
ポイント
- 画面遷移図や操作フローを必ず添付する
- 想定ユーザーと権限ごとの振る舞いを明確にする
- エラーハンドリングは具体的な表示文言まで書く
- 優先度や必須/任意を明記し、開発スコープを明確にする
要件定義書作成の流れ
1. 現状把握・課題分析
まず業務フロー、既存サイトやシステムの機能、利用状況を洗い出します。関係者への聞き取り、アクセス解析、コンテンツ一覧の作成が中心です。例:どのページがよく見られているか、更新に時間がかかる箇所はどこか。
2. 要望収集と優先順位決定
ユーザーや社内の要望を集め、要件を整理します。ユーザーストーリーや要件を「必須/重要/検討」のように分類し、影響度と工数で優先順位を付けます。簡単な例として、ログイン機能は必須、SNS連携は検討など。
3. システム全体像の設計
サイトマップ、ページ種別、システム構成図を作ります。外部サービスとの連携点やデータの流れを明示します。ここで大まかな画面数やAPI連携の有無を決めます。
4. 詳細要件の定義
業務要件、機能要件、非機能要件(性能、セキュリティ、運用)を具体化します。画面遷移図、入力項目、バリデーション、エラーハンドリングなども記載します。
5. 体制・スケジュール・予算の策定
担当者、レビューの役割分担、開発フェーズとマイルストーンを決めます。見積りとリスク、保守運用の負担も明記します。MVP(最小実行製品)を設定し段階的にリリースする計画が有効です。
実務上のポイント
・小さな成果物で早めに確認を繰り返す。・関係者の合意を明文化する(承認フロー)。・変更管理ルールを決める。
CMS要件定義書サンプルテンプレートについて
テンプレートの種類
多くはWordやExcel形式で提供されます。Wordは文章中心の説明や承認フローに向き、Excelは一覧や項目比較、優先度管理に向きます。サンプルはそのまま使えるものも多いです。
テンプレートの選び方
プロジェクト規模(小・中・大)とCMSの種類(パッケージ、クラウド、自社開発)で選びます。小規模なら簡易版、複雑な要件があるなら詳細版を基にします。
カスタマイズの具体例
- 目的・背景を追加して関係者に共有しやすくする
- ページ種別や権限表をプロジェクトに合わせて整理する
- 非機能要件(性能、運用時間)を追記する
WordとExcelの使い分け
Wordは説明と承認に、Excelは設計や工数見積もり、QAリストに使います。両方を併用してリンクを貼る運用が実務では便利です。
運用・管理のポイント
バージョン管理を行い、変更履歴と担当者を明記します。レビュー時のチェック項目をテンプレート内に設けると混乱が少なくなります。
テンプレートチェックリスト(最小)
- 目的・範囲の明記
- 関係者一覧
- 機能一覧(優先度付き)
- 非機能要件
- 受け入れ基準
- 変更履歴
テンプレートはそのまま使うより、プロジェクトに合わせて簡潔に整理すると実務で役立ちます。
CMS要件定義書作成時の注意点
用語定義を必ず入れる
関係者で同じ言葉が違う意味で伝わらないよう、用語集を最初に用意します。たとえば「ページ」「テンプレート」「ユーザー権限」など、具体例を示しておくと誤解を防げます。
目的・背景を明確にする
なぜCMSを導入するのか、期待する成果や制約を明文化します。背景が共有されていると、優先度付けや妥協点の判断が速くなります。
機能要件と非機能要件を分ける
機能(記事作成や公開ワークフロー)と非機能(性能、セキュリティ、可用性)は別項目で記載します。どちらも曖昧だと後工程で手戻りが発生しやすいです。
スコープと優先度を明示する
必須要件と将来的な拡張は区別します。必須・準必須・任意などの優先度を付けておくと、リリース判断が楽になります。
拡張性と運用を見据える
将来の機能追加や他システム連携を想定して設計の余地を残します。運用担当者の作業負荷や保守手順も要件に入れておくと運用後の混乱を減らせます。
レビューと承認フローを定める
関係者によるレビュー回数と承認者を明記します。レビュー履歴を残すことで責任範囲が明確になります。
テスト基準と受け入れ条件を書く
受け入れ時の確認項目や合格基準を具体的に記載します。動作確認の手順やサンプルデータも添えておくと実務で役立ちます。
文書の更新ルールを決める
要件定義書は生きた文書です。変更時の版管理方法や更新責任者を決め、常に最新の状態を保ちます。
まとめ:CMS要件定義書はプロジェクト成功の要
要点の整理
CMS要件定義書は、目的・背景、機能要件、非機能要件、運用・保守を明確にするための設計図です。例として、投稿権限やデザイン切替、バックアップ方針などを具体化すると運用時の迷いを減らせます。
作成時のチェックリスト
- 目的と成功指標を明記する(例:記事更新のリードタイムを半分にする)
- 対象ユーザーと権限を定義する(編集者、管理者など)
- 必要な機能と優先度を洗い出す(必須・必要・将来)
- 運用ルールと保守体制を決める(更新頻度、バックアップ)
- テンプレートやサンプルを活用して標準化する
実務での使い方
要件定義書は関係者の合意形成ツールです。開発前にレビューを行い、実装・テスト・運用の各段階で参照してください。変更は版管理をし、理由と影響を記録します。
最後に
要件定義書を丁寧に作ると、開発コストと後戻りを減らせます。まずはテンプレートを使い、実際のプロジェクトに合わせて簡潔に整えてください。これがプロジェクト成功への近道です。