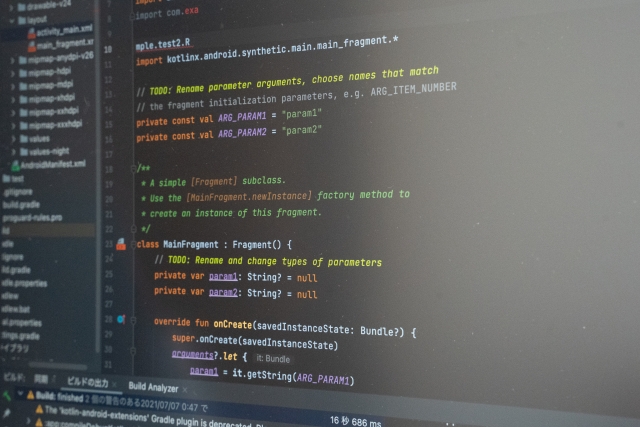はじめに
本章の目的
この章では、本記事の全体像と読み方をやさしく紹介します。AWSでWebアプリケーションを作るときに多く使われる「3層アーキテクチャ」(プレゼンテーション層、アプリケーション層、データ層)について、なぜ学ぶ価値があるのかを分かりやすく説明します。
なぜ3層アーキテクチャが重要か
Webアプリケーションは、見た目・処理・データという役割に分かれます。例えば、ECサイトなら「商品一覧を表示する(見た目)」「注文処理を行う(処理)」「注文情報を保管する(データ)」です。役割を分けると、負荷分散や保守、障害対応がしやすくなります。
本記事で学べること
- AWSの代表的なサービスを使った3層構成例
- 構成のメリットと注意点
- LAMPなど実践的な構築例や運用のコツ
- 最新の発展動向と活用ポイント
読み方のヒント
初めての方は第2章で基礎を押さえ、第3章以降で具体的な図や手順を確認してください。実務に使いたい方は第5章の実践例を先に読むとイメージが掴みやすいはずです。
この後は、まず基礎となるWeb3層アーキテクチャの考え方を順に説明していきます。
Web3層アーキテクチャとは何か
概要
Web3層アーキテクチャは、Webアプリを「プレゼンテーション層」「アプリケーション層」「データ層」に分ける設計パターンです。それぞれ役割を分離し、開発や運用を分かりやすくします。
各層の役割
- プレゼンテーション層: ユーザーに見える画面や入力受付を担当します。例: ログイン画面や商品一覧ページ。
- アプリケーション層: ビジネスの処理を行います。例: ユーザー認証や注文処理のロジック。
- データ層: データの保存・取得を行います。例: 会員情報や注文履歴を格納するデータベース。
なぜ分けるのか(メリット)
層を分けると、担当を分業できます。UIを直してもデータには影響しづらく、性能改善や障害対応が楽になります。再利用性も高まり、同じ処理を別の画面から使えます。
身近な例でイメージ
ネットショップを想像してください。商品一覧はプレゼンテーション層、カート計算はアプリケーション層、在庫情報はデータ層です。各部分を別々に改良できるため、全体の変更が速く安全になります。
AWSでの3層アーキテクチャの構成例
概要
AWSでは、プレゼンテーション層・アプリケーション層・データ層を組み合わせて、スケーラブルで高可用な3層アーキテクチャを構築できます。用途や負荷に応じてサービスを選ぶと、運用効率とコストのバランスを取りやすくなります。
プレゼンテーション層(例)
- Amazon CloudFront:静的コンテンツを高速配信します。CDNとして使うとユーザー体験が向上します。
- Application Load Balancer(ALB):HTTP/HTTPSの負荷分散を担います。複数のEC2やECSへ振り分けます。
- Amazon API Gateway:API公開に便利で、認証やレート制御を簡単に設定できます。
アプリケーション層(例)
- AWS Lambda:サーバーレスで短時間処理やイベント駆動に向きます。運用が容易です。
- Amazon ECS / Fargate:コンテナでの実行に適し、スケールを自動化できます。
- Amazon EC2:細かな制御や独自ミドルウェアが必要な場合に有効です。
データ層(例)
- Amazon RDS:リレーショナルデータベースをマネージドで提供します。Multi-AZ構成で冗長化できます。
- Amazon DynamoDB:キー・バリュー型の高速NoSQLでスケーラブルです。
- Amazon S3:静的ファイルやバックアップの保存に使います。
構成例
- サーバーレス構成:CloudFront + API Gateway + Lambda + DynamoDB/S3。短期間の開発やトラフィック変動が大きい場合に有利です。
- EC2ベース構成:CloudFront + ALB + Auto Scaling(EC2)+ RDS。レガシー移行や細かいチューニングが必要な場合に適します。
- コンテナ構成:ALB + ECS/Fargate + RDS/DynamoDB。マイクロサービス化に向きます。
運用のポイント
VPCやサブネットの分離、セキュリティグループとIAMでの権限最小化、CloudWatchでの監視とアラート、バックアップ(RDSスナップショット、S3ライフサイクル)を組み合わせて運用性を高めてください。
3層アーキテクチャのメリット・特徴
ブログの記事をどう書けばいいかわからない、という疑問をお持ちではありませんか? 本章では、AWSなどで採用される3層アーキテクチャの主な利点をわかりやすく説明します。具体例を交えて、どのような場面で役立つかを示します。
モジュール化・保守性の向上
各層(表示層/アプリ層/データ層)が独立しているため、影響範囲を小さくできます。たとえば、画面表示だけを改修してもデータ層に手を加える必要が少なく、テストやリリースが楽になります。
スケーラビリティ
負荷が増えたら表示層やアプリ層だけを増やせます。オートスケールやロードバランサーを使えば、アクセス急増時でも応答を保てます。コスト効率よく拡張できます。
高可用性・冗長化
冗長構成やフェイルオーバーを各層で設定できます。たとえばデータベースを複数リージョンや複数AZで冗長化すると、障害時のサービス継続性が高まります。
セキュリティ強化
層ごとにアクセス制御やネットワーク分離、暗号化を行えます。公開すべき機能を表示層に限定し、重要なデータはデータ層で厳重に守る、といった実装がしやすいです。
運用負荷の軽減
マネージドサービスや監視ツールを組み合わせることで運用負荷を下げられます。自動バックアップやログ収集、アラート設定により運用効率が向上します。
これらの特徴により、開発スピードと運用の安定性を両立できます。小規模から大規模まで幅広いシステムで有効な設計です。
LAMP環境や実践的な構築例
構成概要
LAMP(Linux, Apache, MySQL, PHP)をAWSで3層に分けると、ALBがWeb層の入り口、EC2がアプリ層、RDSがデータ層を担います。Eコマースや業務アプリでよく使われる実務的構成です。
ネットワークとサブネット
VPCを用意し、公衆向けのパブリックサブネットにALB、アプリとDBはプライベートサブネットに配置します。NATゲートウェイでEC2の外向き通信を許可します。
Web層(ALB)
ALBでHTTPSを終端し、ターゲットグループにEC2を配下登録します。ACMで証明書を管理すると手間が減ります。
アプリ層(EC2)
Amazon LinuxやUbuntuでPHP-FPMとApacheを設定します。Auto Scalingを使い負荷に応じてインスタンス数を調整します。セッションはElastiCache(Redis)やRDSに移すとスケールしやすくなります。
データ層(RDS)
RDS(MySQL互換)をマルチAZ構成で運用し、バックアップと自動リストアを有効にします。パラメータは本番負荷に合わせて調整します。
実運用での工夫
・ファイルはS3に保存してEC2間で共有する。
・デプロイはAMIやCodeDeployでロールアウトを自動化する。
・監視はCloudWatch、ログはCloudWatch LogsやS3で保管する。
・セキュリティはセキュリティグループとIAMで最小権限を徹底する。
これらを組み合わせると、可用性・運用性の高いLAMP環境が実現できます。
AWS 3層アーキテクチャの発展・最新動向
サーバーレス化と自動スケーリング
近年はミドル層やプレゼンテーション層でサーバーレスを採用する例が増えています。たとえば、API Gateway+AWS LambdaでWeb APIを作ると、アクセスに応じて自動でスケールし、運用負荷とコストを下げられます。バッチ処理はFargateやStep Functionsで柔軟に組めます。
生成AIサービスとの連携
生成AI(例:Amazon Qなど)をフロントや業務ロジックに組み込み、チャット機能や自動要約、コンテンツ生成を実現できます。AIは外部APIとして呼び出し、応答をキャッシュして応答性を改善する設計が現実的です。
データ統合と分析
ETLにはAWS GlueやGlue Studioを使い、データレイクから集計、機械学習への流し込みを自動化します。データ層での整形を自動化すると、アプリ層の開発が楽になります。
運用・セキュリティの進化
Observed性はCloudWatch、X-Ray、OpenTelemetryで強化します。認証はCognitoやIAM、細かいアクセス制御はリソースポリシーで対応します。
インフラ自動化とベストプラクティス
インフラはCDKやTerraformでコード化し、CI/CDで環境を安定化します。小さなサービス単位で可観測にして、段階的に改善する運用が薦められます。
まとめ・活用ポイント
今回解説したAWSの3層アーキテクチャは、スケーラビリティ・保守性・可用性を高める実践的な設計です。目的や要件に合わせ、EC2ベース、サーバーレス、ハイブリッドのいずれかを選べば、柔軟に最適化できます。
設計の選び方
- EC2ベース:細かい制御が必要なときに有効です(例:独自ミドルウェアを使う)。
- サーバーレス:運用工数を減らしたいときに向きます(例:LambdaでAPI実装、S3で静的配信)。
- ハイブリッド:既存資産とクラウド利点を両立したいときに便利です。
運用と安定化のポイント
- 自動スケールやロードバランサーで負荷変動に備えましょう。
- 監視はCloudWatchなどでログとメトリクスを一元化します。
- IaC(CloudFormationやTerraform)で再現性ある構成管理を行います。
セキュリティ・コスト管理
- 最小権限のIAM設計、バックアップと多AZ構成で可用性を確保します。
- 使用状況を定期確認し、インスタンスタイプや課金設定を見直してコスト最適化します。
実装前に要件を明確にし、小さく始めて段階的に改善することで、安定したシステム運用が可能になります。活用の幅は広いので、まずは試験環境で設計を検証してください。